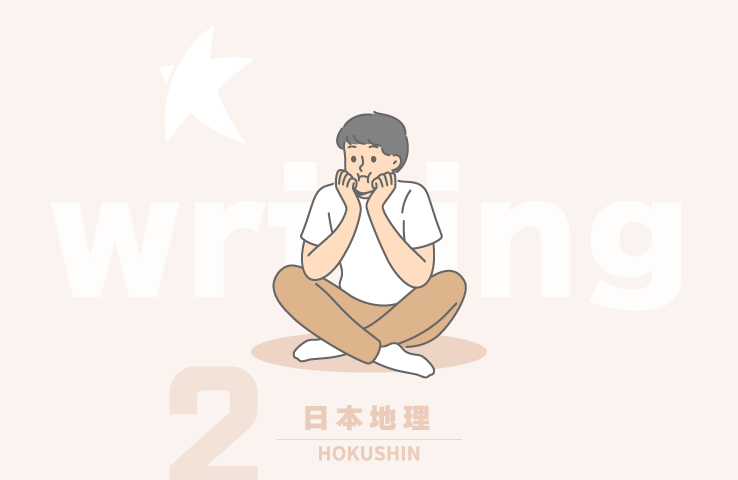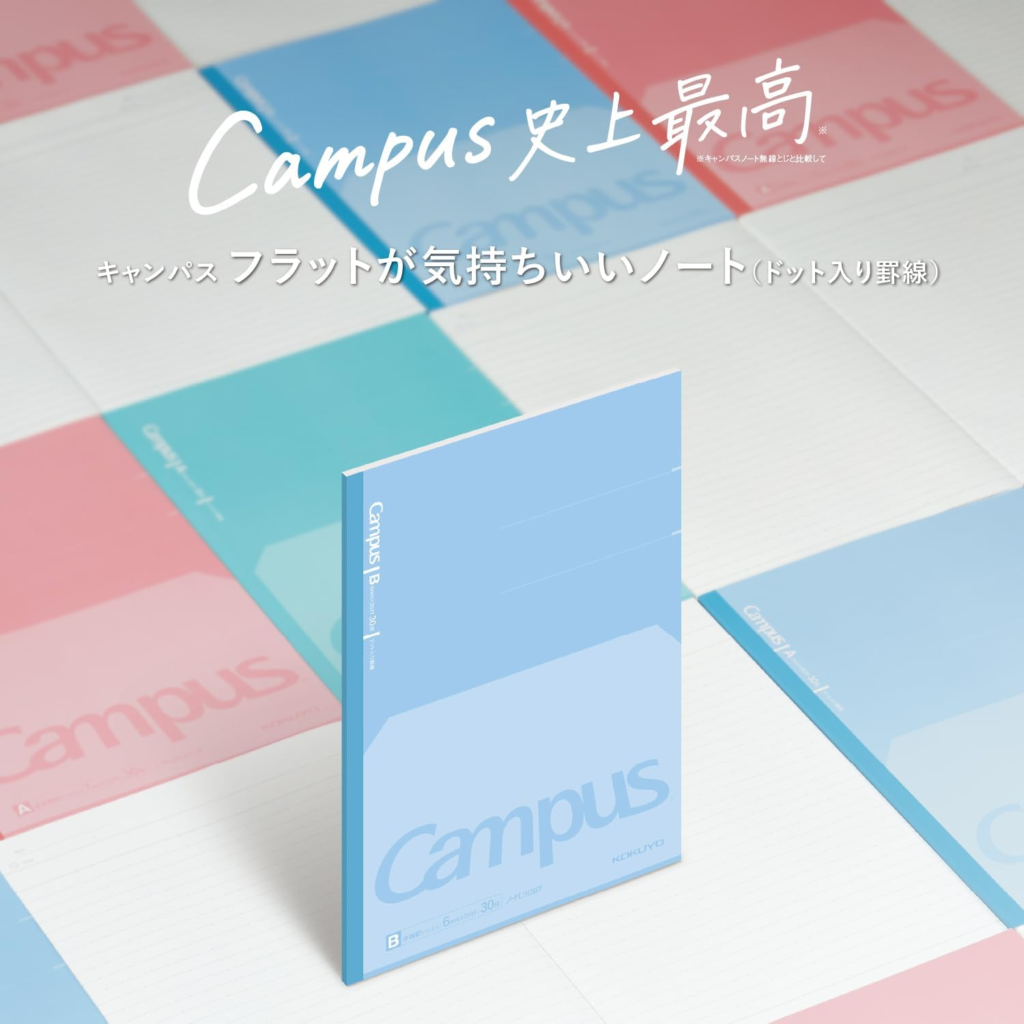このページのもくじ
日本地理
農業

出荷時期を早めることで、価格が高い冬から春に出荷している。(促成栽培)
促成栽培
野菜を「いつもより早く育てて出荷する工夫」と覚えておくとわかりやすいでしょう。日本各地では、気候や技術をいかして、トマトやキュウリなどのさまざまな野菜が促成栽培されています。宮崎県や高知県のように気候が温暖で日照時間が長い地域では、ハウス栽培などを利用して早い時期から出荷することができます。これは、普通なら寒い季節にあまり育たない野菜を、暖房や温度管理などの工夫によって早めに収穫する方法です。
ポイント
①温暖な気候
宮崎県や高知県は冬でも気温が比較的高いため、ハウス内の温度をあまり上げなくても促成栽培がしやすい環境です。
②ハウス栽培などの設備
ビニールハウスを使って温度や湿度を管理し、野菜が育ちやすい状態を保っています。
③市場への早期出荷
普通なら春や夏にとれるピーマンやナスでも、促成栽培をすることで冬から春にかけて出荷できるようになります。
④コストと利益のバランス
ハウス設備や暖房代など費用はかかりますが、早い時期に出荷すると高い値段で売れることが多いため、経営面でもメリットがあります。
いちごの促成栽培
いちごといえば春にたくさん出回るイメージがありますが、促成栽培によって冬のあいだから出荷されることが多くなりました。温暖な気候をいかして、静岡県や福岡県、熊本県などで盛んに促成栽培されています。また、いちごの生産量が多い栃木県や福岡県などでも、ハウスを使った栽培が一般的です。
出荷時期を遅らせることで、夏の時期に出荷している。(高原野菜)
高原野菜とは
標高の高い地域で育てられる野菜のことです。山あいの涼しい気候をいかして、通常より暑さの影響を受けにくく、シャキッとした食感やみずみずしさを保ちやすいのが特徴です。夏から秋にかけて高原のレタスがいっせいに収穫され、全国のスーパーや市場に出荷されます。普通なら夏は「暑くてレタスが育ちにくい時期」ですが、高原野菜のおかげで新鮮なレタスを手に入れられるのです。長野県の高原レタスは、標高の高い地域ならではの「夏でも涼しく昼夜の温度差が大きい」という環境を活かして育てられます。そのため、暑い時期でもシャキシャキとした食感やみずみずしいレタスを出荷できるのです。これが高原野菜の大きな魅力といえます。促成・抑制というよりも「土地の特性」を利用した栽培で、夏~秋に出荷することが多い。
大都市に近い条件を活かして、輸送費を安くおさえ鮮度が良い状態で出荷している。(近郊農業)
近郊農業
都市の近くで行われ、新鮮な野菜や果物を素早く消費者に届けることができる農業です。首都圏や近畿圏、中京圏などの大都市周辺で発展しており、とくに葉物野菜やハウス栽培の作物が多く作られています。一方で、都市開発による農地の減少や地価の高さなど、課題も少なくありません。こうした近郊農業のおかげで、わたしたちは日々、新鮮で安心な野菜を身近なお店で手に入れることができるのです。
広大な耕地面積をもつ農家の割合が大きく、大規模な農業が行われている。
広大な面積と大規模経営
北海道は日本の中でも耕地面積が非常に広く、畑作(はたさく)や酪農などを大規模に行うことが多いです。機械化が進んでいて、一つの農家あたりが管理する農地の面積が本州に比べて大きいのが特徴です。
北海道の農業の収穫量を安定させる工夫
耕地をいくつかの区画にわけて、異なる作物を順番に生産している。同じ畑で同じ作物ばかり作ると、連作障害や病害虫の被害が増えます。小麦→馬鈴薯(ばれいしょ)→豆類→甜菜(てんさい)のように作物を順番に変えることで、土壌の疲れを防ぎ、収穫量を安定させています。
大消費地に遠いため、飲用の割合が小さく、加工用の割合が大きい。
北海道の生乳
日本最大の生産量を背景に豊富な供給力を持ち、飲用・加工用の両面で重要な役割を担っています。地理的条件や輸送コスト、飲用乳の消費動向などから、本州などと比較すると加工用へ回る割合が高いことが大きな特徴です。加工品としてはチーズやバター、脱脂粉乳をはじめとする多様な商品が作られ、北海道ブランドとして国内外で高い評価を得ています。
りんごが有名なので、果実の産出額の割合が大きい。
果樹(リンゴ)中心の構成
リンゴの圧倒的存在感。青森県といえばリンゴの産地として全国的に知られています。産出額においてもリンゴは県全体の農業を支える中心的存在で、全国トップの生産量を誇ります。リンゴの栽培技術や品種改良が進み、高糖度やブランド化された品種が登場することで、国内外への販路拡大や輸出が活発化している点も特徴です。
冬の時期に降雪量が多く、農作業を行うことが困難になるため、副業が行われている。
「副業」の背景と特徴
北陸地方は豪雪地帯であり、稲作の作付けが終わる秋から春先にかけては農作業が大きく制約されます。そのため、農家は農閑期に収入を確保するための副業を伝統的に行ってきました。
伝統的な副業の例
織物・編物・染物などの手工芸。越後縮(えちごちぢみ)や塩沢紬(しおざわつむぎ)など、新潟県を中心に発達した織物は冬期副業の代表的な例です。
和紙づくり
雪国特有の寒冷な気候と豊富な水資源を利用して、和紙の生産が行われる地域もあります。味噌・醤油造り、漬物などの食品加工。雪国では保存食文化も発達しており、冬場に行う加工食品づくりを通じて収入を補う家もありました。
夜間に照明をあてることで、菊が開花する時期を遅らせて出荷している。
渥美半島の電照菊栽培
温暖な気候と長い日照時間、豊富な水資源を活かしながら、電照技術で開花時期を調整して需要期に合わせて出荷することで高い収益性を確保してきました。大規模ハウスや高度な栽培技術の導入により、全国有数の産地として成長しています。
自給率は下がり、就業者数も減少している。
飼養戸数は減少し、一戸あたりの飼養頭数は増加している。
飼養戸数の減少
乳用牛を飼育する農家(飼養戸数)は年々減少しています。これは、労働力不足や経営の厳しさ、後継者不足などの影響を受けて、酪農をやめる農家が増えているためです。
一戸あたりの飼養頭数の増加
一方で、一戸あたりの飼養頭数(農家1軒あたりが飼う牛の数)は増加しています。これは、大規模経営の進展によるもので、搾乳の機械化(搾乳ロボットなど)経営の効率化(大型の牧場経営)が進んでいるためです。
変化の理由
小規模酪農家の廃業 → 経営が厳しく、やめる農家が増加。大規模化の進展 → 機械を活用し、一軒あたりの牛の数が増加。労働力不足 → 人手が減る中で、効率的に運営するための工夫。
つまり、乳用牛を飼う農家は減っているが、1軒あたりの牛の数は増えているというのが、日本の酪農の大きな変化です。
生活

石油や石炭などの燃料の輸入に便利な臨海部につくられている。
歴史的な景観を守ること。
台風による強風にそなえるため、塀が石でつくられている。
屋外の冷たい空気が入らないように、玄関が二重につくられている。
冬の季節風の影響で、降雪量が増えるため、出入り口が地面よりも高い位置につくられている。
東京に通勤する人が多いため、通勤時間が多くなる。
通勤通学に鉄道・バスを使う割合が小さいほど、100世帯あたりの乗用車保有台数が多い。
水力発電に利用されている。
訪れた人々が自然を楽しめるようにすることと、環境を守ることの両立を目指す取り組み。
都市部の気温が、周辺部の気温よりも高くなる現象。
水を一時的にためて、洪水を防いでいる。
宿泊者総数は夏に多いが、外国人宿泊者数は冬に多い。
工業

輸出品は繊維原料から機械類へと変化した。
原材料の入手や製品の輸送に便利な高速道路付近。
石油などの原材料を大型貨物船で輸入するのに便利な臨海部。
鉄鉱石の輸入先である中国や、石炭の山地である筑豊炭田に近いため。
交通の便が良くなり、製品出荷額が大きく増加した。
重化学工業の割合が大きくなり、石油を利用する割合も大きくなった。
第三次産業の割合は大きくなり、第一次産業の割合は小さくなっている。
海外生産台数が、国内生産台数を上回った。
気候

北西の季節風が日本海の上をとおり、水蒸気を含み、山地にぶつかることで冬に雪や雨を多く降る。
季節風が山地にさえぎられるため、降水量が少ない。
降水量が少ないため、農業用水の確保でため池をつくる工夫がされている。
西側は湿った季節風が山脈にぶつかり、雪を降らせる。東側は山脈をこえた乾いた風が吹くため、晴れの日が多い。
交通

電子部品のような軽量で高価なものを輸送する。
二酸化炭素排出量を減らすこと。
韓国からの距離が短く、飛行時間も短いため韓国の利用が特に多い。
周辺の住宅に伝わる騒音を小さくするため。
地形

火山の噴出物などが積もってできた地形。水はけがよいため稲作や畜産が盛ん。
海や湖などの河口部分付近にできる低く平らな地形。
川が山間部から平野や盆地に流れ出てできた地形。水はけがよいため果樹栽培が盛ん。
低地に比べて必要な水を得にくいため、稲作に利用しにくい。
波が少なく、水深が深いため養殖に適している。
上流から河口までの標高差が大きく、距離が短いため急流である。
人口

大学進学を機に、県外へ出ていく人が多いため。
昼間は都内に通勤・通学する人が多いため。
漁業

暖流の黒潮[日本海流]と寒流の親潮[千島海流]がぶつかることで、潮境[潮目]となるため。
沿岸国が、鉱産資源や水産資源を利用する権利をもつ水域のこと。
南鳥島のような離島が多いため。
まとめ
解説部分を今後補強予定~
ひとまず問題と答えだけ~