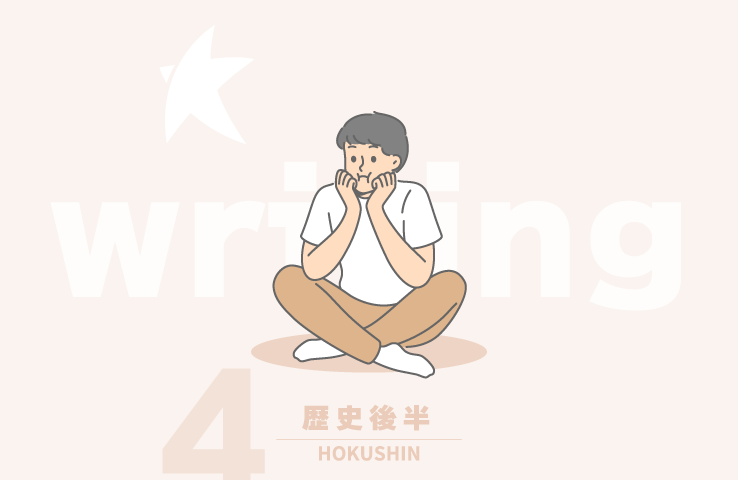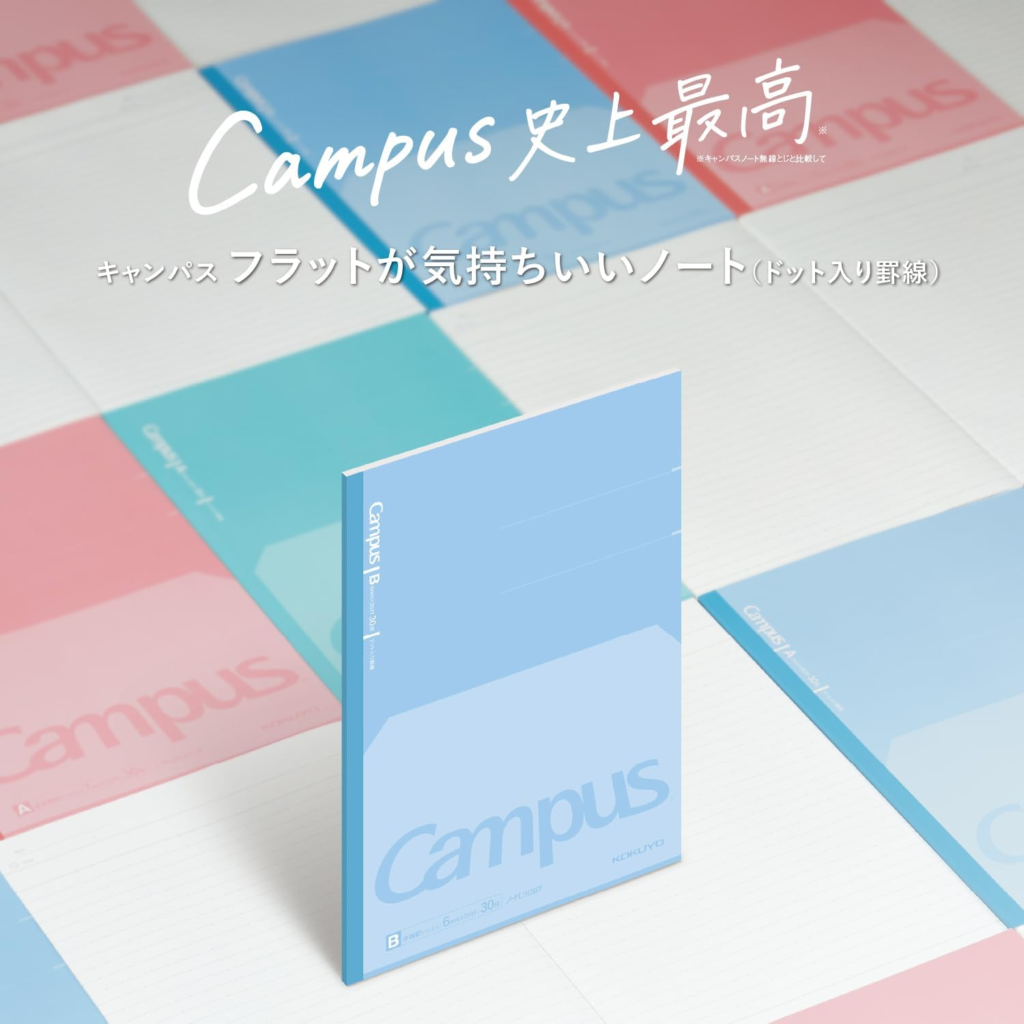このページのもくじ
歴史後半
江戸
朱印状を用いた貿易で、東南アジア地域に日本人が生活する日本町が形成された。
日本町とは何か
日本町とは、戦国時代から江戸時代初期にかけて、日本人が海外に移住して形成した集落や町のことです。このような地域は東南アジアを中心に広がり、たとえばタイやフィリピン、ベトナムなどに見られました。
日本町が形成されたきっかけ
これらの日本町が形成されたきっかけには、日本と海外との貿易の発展があります。特に、朱印船貿易という制度が重要な役割を果たしました。朱印船貿易は、江戸幕府や豊臣政権が外国と貿易を行う際に発行した許可証(朱印状)を持った船による貿易です。この貿易を通じて、多くの日本人が海外に渡り、現地で商業活動を行ったり、定住するようになりました。
日本町の特徴と貿易の内容
日本町では、日本人だけでなく現地の人々や他国からの移民との交流もありました。たとえば、日本の文化や技術が伝わる一方で、現地の文化や風習も日本に影響を与えました。また、日本町は日本からの輸出品である銀や刀剣、漆器などを扱い、逆に現地からは香辛料や絹、陶磁器などが輸入されました。
それ以前の貿易との違い
朱印船貿易は、それ以前の貿易とは異なり、規模、組織化、現地の治安、国内の状況といったさまざまな条件が整ったため、日本町が形成されました。これにより、日本人の海外進出が活発になり、現地での交流や商業活動の基盤が築かれたのです。
タイ(アユタヤ)の日本町跡
アユタヤでは、日本町の存在が確認されており、現在は「アユタヤ日本人村」として記念されています。ここには日本町の歴史を紹介する博物館があり、当時の生活や貿易活動に関する資料が展示されています。
朱印状と勘合の違い
| 比較項目 | 朱印状 | 勘合 |
|---|---|---|
| 使用時期 | 戦国時代末期~江戸初期 | 室町時代 |
| 対象地域 | 東南アジア | 中国(明) |
| 発行方法 | 幕府や政権が文書を発行 | 明と日本の割符(札)を照合 |
| 目的 | 貿易の信頼性向上と秩序維持 | 貿易の統制と違法防止 |
| 特徴 | 朱印(赤い印章)が押される文書 | 割符を照合して公式性を確認 |
親藩や譜代大名は江戸の近くに、外様大名は江戸から遠い地域に配置された。
江戸時代の大名の配置
幕府が権力を安定させるための戦略的な政策でした。親藩、譜代、外様という分類に基づき、それぞれの大名に役割を与えつつ、監視と統制を徹底していました。この配置の工夫により、大名が結束して幕府に反抗するのを防ぎ、約260年にわたる江戸時代の平和が維持されたのです。
配置の戦略
大名の配置には幕府の支配を強固にするための明確な戦略がありました。
①江戸の防衛
江戸城を中心に、親藩や譜代大名を近くに配置。
特に関東地方には多くの譜代大名が置かれ、幕府の拠点を守りました。
②外様大名の監視
外様大名は、幕府に反抗する可能性があると考えられ、遠隔地に配置されました。
他の外様大名同士が連携しにくいよう、隣接させず分散して配置されました。
③要地の抑え
幕府が特に重要とした地域(交通の要所や港など)には、信頼のおける親藩や譜代大名を配置。
例えば、東海道や西国街道などの主要街道沿いに幕府直轄地や親藩が置かれました。
④参勤交代の影響
大名は参勤交代で江戸と領地を行き来する必要がありました。この仕組みにより、遠隔地にいる大名も経済的・軍事的に負担を強いられ、幕府の統制が強まりました。
大名の分類
大名は主に以下の3つの種類に分けられ、それぞれ異なる役割を担っていました。
①親藩(しんぱん)
徳川家の一門や近い親族。たとえば、水戸藩、尾張藩、紀州藩のような大藩がこれに該当。幕府の中核を支える立場で、重要な地域(江戸や京の周辺)に配置されました。
②譜代大名(ふだいだいみょう)
江戸幕府成立以前から徳川氏に仕えていた家臣。石高が比較的小さい場合もありましたが、幕府の行政や軍事を支える重要な役割を果たしました。関東地方や東海地方など、江戸に近い場所に配置されることが多かったです。
③外様大名(とざまだいみょう)
関ヶ原の戦い以降に徳川氏に従った大名。幕府に対する信頼度が低いと見なされ、遠隔地(九州や東北地方など)に配置されることが多かったです。毛利氏(長州藩)や島津氏(薩摩藩)などの大藩が含まれます。
大名と石高の基準
江戸時代において、石高1万石以上の領地を持つ武士が大名とされました。それ以下の石高を持つ者は旗本や御家人と呼ばれ、大名とは区別されました。
小大名:石高1万石~10万石程度の大名。
中大名:石高10万石~50万石程度の大名。
大大名:石高50万石以上の大名。
石高とは何か
石高は、土地の収穫量をお米の量で表した単位です。1石は、大人1人が1年間に食べる米の量とされ、1石=約150kgに相当します。つまり、石高が高いほどその土地の収穫量が多く、大名の経済力も高いことを示します。
検地とは
検地は、土地の面積や質、生産量を調査して記録する制度です。この調査によって土地の石高が決定されました。検地を実施することで、領主は領地の収入や住民の負担を正確に把握し、管理することが可能になります。
太閤検地と江戸時代の検地の違い
太閤検地の成果をもとに、江戸時代の幕府や藩も検地を行いましたが、いくつかの違いがあります。
| 比較項目 | 太閤検地 | 江戸時代の検地 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 豊臣秀吉(中央政権が統一的に実施) | 各藩や幕府が個別に実施 |
| 規模 | 全国規模 | 藩単位または幕府直轄地のみ |
| 主な目的 | 全国統一的な土地制度の確立 | 年貢徴収や領地経営の安定 |
| 管理体制 | 検地帳に基づく全国的な管理 | 各藩独自の管理体制 |
| 身分区分の強調 | 武士と農民の分離を徹底 | 原則を維持しつつも地域差があった |
関ヶ原の戦い
1600年に岐阜県関ケ原で起こった日本の歴史上最大の戦いで、全国を統一する権力が徳川家康に移るきっかけとなりました。戦国時代の終わりを告げ、江戸時代の基盤を築いた重要な戦いです。
東軍(徳川家康)
家康を中心に、天下統一を目指す有力な大名たちが集まりました。
西軍(石田三成)
豊臣政権を守ろうとする大名たちが集まりました。
キリスト教信者を発見すること。
絵踏(えふみ)
は、江戸時代に幕府がキリスト教徒(隠れキリシタン)を見つけ出すために行った政策です。目的はキリスト教の禁止を徹底し、幕府の支配体制を安定させることにありました。絵踏は1630年代から幕末まで約200年間続きました。
絵踏の方法
①村や町で住民を集め、キリストや聖母マリアを描いた絵や像を用意して踏ませました。
②キリスト教徒であれば聖なる絵や像を踏むことを拒むと考え、そうした行動を取った人を隠れキリシタンと判断しました。
③キリスト教徒と疑われた人は取り調べを受け、拒否すれば改宗を求められ、場合によっては厳しい拷問や処刑が行われました。
政治的な危険性
①信仰による幕府への反抗の可能性
キリスト教信者は神(キリスト)を最優先とし、場合によっては世俗の権力(幕府)よりも信仰を重視する可能性がありました。幕府は、大名や領民が自らの支配を超えた価値観に従うことを大きな脅威と感じていました。
②島原・天草一揆の影響
1637年に起こった島原・天草一揆は、重い年貢に苦しんだ農民がキリスト教信者を中心に反乱を起こしたものです。この一揆をきっかけに、幕府はキリスト教が民衆を団結させ、反乱を引き起こす力を持つと確信しました。
「踏絵(ふみえ)」と「絵踏(えふみ)」
どちらも江戸時代に行われたキリスト教徒を発見するための行為に関係しますが、指しているものや視点が異なるため、間違えないようにするにはそれぞれの意味や使い方を整理して覚えることが大切です。踏絵は「モノ」:踏む対象(絵や金属板)。絵踏は「行為」:その踏絵を使った調査や行動全般。
覚えやすい例文
「踏絵を使って絵踏を行う。」「絵踏の対象となったのが踏絵だ。」
キリスト教対策①:バテレン追放令(禁教令)
1587年に豊臣秀吉が発令した「伴天連追放令」を、江戸幕府も継承しました。「伴天連(ばてれん)」とはキリスト教の宣教師のことを指します。外国人宣教師を日本から追放し、キリスト教の布教活動を禁止しました。宣教師がいなくなることで新たな布教を防ぎ、キリスト教が広まるのを抑えました。
キリスト教対策②:宗門改(しゅうもんあらため)
各地域で住民の宗教を記録する制度です。仏教寺院を通じて管理され、住民は「自分が仏教徒である」ことを証明する必要がありました。檀家制度を通じて、すべての家庭が必ずどこかの仏教寺院に属することを義務付けました。毎年、各地の寺院が住民の信仰状況を確認し、報告しました。キリスト教信者を発見しやすくし、仏教を通じて社会統制を強化しました。
キリスト教対策③:海外との接触の遮断(鎖国政策)
幕府はキリスト教と密接な関係があったポルトガルやスペインとの貿易を禁止しました。1639年、ポルトガル船の来航を全面的に禁止。オランダや中国(明)とのみ貿易を許可し、布教活動を行わない国との関係を重視しました。布教を目的とする外国人宣教師やカトリック諸国の影響を完全に排除しました。
大名が一年おきに、江戸に滞在する制度。
参勤交代(さんきんこうたい)
江戸時代に江戸幕府が大名を統制するために設けた制度です。大名は定期的に江戸と自分の領地を行き来し、一定期間江戸に滞在することを義務付けられました。この制度は幕府が大名を監視し、統制を強化する目的で作られました。
参勤交代の内容
①基本ルール
大名は1年おきに自分の領地と江戸を行き来することが義務付けられました。江戸に滞在する期間は通常1年で、その後は領地に戻ってまた1年間過ごすというサイクルです。
②家族の江戸住まい
大名の妻子は江戸に常住することが義務付けられていました。これにより、大名が幕府に反抗した場合、家族を人質として抑える効果がありました。
③行列の規模
大名は参勤交代の際、大名行列を組み、領地から江戸まで移動しました。大名行列の規模は石高(領地の収入)に応じて決まり、石高が多い大名ほど大規模な行列を組む必要がありました。
参勤とは
参:領地から江戸に向かい、将軍に対して忠誠を示す。
勤:江戸滞在中に将軍の家臣としての役割を果たす。
これに「交代」が加わり、領地と江戸を定期的に行き来する制度として成り立っています。
江戸では?
江戸滞在中の大名の生活は、将軍への忠誠を示しながら、自藩の運営を続け、幕府や他の大名との関係を維持する多忙なものでした。参勤交代は単なる移動や形式的な儀礼ではなく、幕府の統制のもとで大名が政治的・社会的責任を果たすための重要な制度だったのです。
江戸での暮らしに多くの費用がかかったため。
江戸での滞在費用
大名は江戸に滞在する間、藩邸での生活費を自ら負担する必要がありました。江戸での生活費には、大名や家族の生活費だけでなく、多数の家臣の給与や食料、接待費なども含まれました。江戸での滞在期間が長いため、これが財政を圧迫しました。
移動費用の負担
参勤交代では、大名が家臣や従者を連れて領地から江戸まで行く「大名行列」を組む必要がありました。この行列の規模は、藩の石高(収入)に応じて決められ、石高が高いほど大規模な行列を求められました。道中の宿泊費、食料費、馬や駕籠の使用料などが必要で、移動そのものに膨大な費用がかかりました。
藩の財政が苦しくなること
短期的には幕府にとって大名の統制を強化するメリットがありました。しかし、財政難が長期化すると地方統治の弱体化や経済的な停滞、さらには幕府そのものの財政悪化につながり、江戸時代後期には幕府の支配体制そのものを揺るがす要因となりました。このように、参勤交代による大名の財政難は、幕府にとって一長一短の問題であったといえます。
幕府が日本人の海外渡航を禁止したため。
日本町が衰退した主な理由
江戸幕府の鎖国政策と日本人の海外渡航禁止です。これにより、日本町を支えていた日本人商人や移住者が減少し、経済的基盤が崩壊しました。また、現地の政治・経済の変化や、幕府のキリスト教禁止政策も日本町の消滅に拍車をかけました。結果として、日本町は歴史の中で重要な役割を果たしながらも、徐々にその存在を失っていきました。
日本人の海外渡航禁止(1635年の鎖国政策)
1635年、江戸幕府は日本人の海外渡航を禁止し、すでに海外に移住していた日本人の帰国も禁じました。これにより、日本町を支えていた日本人商人や移住者の数が減少し、現地での日本人コミュニティの維持が難しくなりました。
朱印船貿易の終焉
朱印船貿易は日本町の形成に大きく貢献しましたが、幕府の鎖国政策により徐々に縮小し、最終的に途絶えました。朱印船貿易の停止により、日本町の商業活動が大きな打撃を受け、経済的基盤が崩れました。
幕府のキリスト教禁止政策
日本町ではキリスト教を信仰する日本人も多く、キリスト教徒に対する迫害や取り締まりの影響で、日本町の住民が減少しました。特にフィリピン(マニラ)の日本町では、住民の多くがキリスト教徒であったため、幕府の政策が直接的な衰退要因となりました。
仏教徒であることを証明する役割。
寺請証文(てらうけしょうもん)
江戸時代において人々が自分の宗教を証明するための重要な書類です。この証文には、その人がどこの寺院(檀那寺、だんなでら)に所属しているかが記載されており、主に以下の役割を果たしました。寺請証文は、江戸幕府がキリスト教禁止の徹底と住民の宗教的・社会的管理を行うために欠かせないものでした。寺請証文そのものは、江戸時代の制度とともに廃止され、現在では存在しません。ただし、檀家制度や寺院で発行される供養に関する証明書など、寺請証文に由来する習慣や仕組みが部分的に現代に残っています。
仏教徒であることの証明
寺院が「この人は私たちの寺の檀家であり、仏教徒です」と幕府や地方の行政に対して保証することを指します。これにより、その人がキリスト教徒ではないことが証明されました。
「寺請(てらうけ)」とは
文字通り「寺院が請け負う」という意味です。江戸時代における寺請制度では、住民一人ひとりの宗教的な所属を、地元の寺院が証明する役割を担っていました。この「請け負う」という言葉には、寺院がその人が仏教徒であることを保証するという意味が込められています。
ポルトガル船の来航を禁止した。
島原・天草一揆(1637年~1638年)
江戸幕府は1639年にポルトガル船の来航を全面的に禁止しました。この禁止措置は、幕府が進めていた鎖国政策の完成を象徴するものであり、日本国内でのキリスト教の完全な排除と、外国勢力の影響を断つことを目的としていました。
島原・天草一揆の概要
島原・天草一揆(しまばら・あまくさいっき)は、1637年から1638年にかけて、現在の長崎県島原半島と熊本県天草諸島で発生した、重税や圧政に苦しんだ農民たちがキリスト教信仰を糧に立ち上がった反乱でした。しかし、一揆は幕府の圧倒的な軍事力によって鎮圧され、その後のキリスト教徒への弾圧や鎖国政策の強化につながりました。この出来事は、江戸時代における民衆の抵抗と幕府の支配体制の厳しさを象徴する重要な歴史的事件です。
なぜポルトガル?
キリスト教布教の中心的役割を担い、布教と貿易を結びつけて活動していたことが大きな理由です。さらに、ポルトガルがスペインと密接に結びつき、植民地化の恐れがあったことも警戒されました。他方で、オランダや中国のように布教活動を行わない国々は許可され、ポルトガルは特に危険視されて排除されました。このように、幕府のポルトガル排除政策は、キリスト教禁止と鎖国政策を徹底するための最終的な手段だったといえます。
オランダはキリスト教の布教を行わなかったため。
許された国:オランダ
オランダとの貿易は、長崎の出島に限定して行われました。出島は、外国人の居住や活動を監視しやすい場所として設けられた人工の島です。日本から輸出されたもの:銀、銅、漆器など。日本に輸入されたもの:薬品、学術書、織物、ガラス製品など。
オランダが貿易を許された理由
キリスト教布教を行わなかった
幕府はキリスト教を日本の秩序を乱すものとみなし、布教活動を強く警戒していました。オランダ(プロテスタント)は、スペインやポルトガル(カトリック)とは異なり、布教活動に積極的ではありませんでした。オランダ商人は「貿易のみ」を目的とし、宗教的な影響を日本に与えないことを幕府に約束しました。
ポルトガルとの対立を利用
オランダは、スペインやポルトガル(カトリック諸国)と対立しており、日本に対してもこれらの国々の情報を提供していました。幕府はオランダを利用することで、ポルトガルやスペインの脅威に対抗しようとしました。
世界の情勢に関する情報
オランダ商館長は定期的に幕府に「オランダ風説書(ふうせつがき)」を提出し、ヨーロッパや世界の政治・経済・軍事に関する情報を報告しました。幕府はこれを通じて、西洋諸国の動向を把握し、特にスペインやポルトガルといったカトリック国の活動を監視しました。
西洋医学の知識
オランダは、西洋医学の知識や医薬品を日本にもたらしました。これが、江戸時代後期の蘭方医学(らんぽういがく)の発展につながりました。代表的な事例として、杉田玄白らによる「解体新書」(1774年)の出版があります。これはオランダ語の医学書を翻訳して作られたもので、西洋の人体解剖学を日本に広めました。
科学技術と学術書
オランダとの貿易を通じて、西洋の天文学、物理学、化学、地理学に関する学術書が輸入されました。これらの知識は、蘭学(らんがく)と呼ばれる学問の基盤を形成し、日本の科学技術の向上に貢献しました。
天文学:暦の改訂に役立てられ、西洋式の天文学的な考え方が導入されました。
地理学:日本が世界の中でどのような位置にあるかを理解するための地図や地理書が輸入されました。
新田開発で耕地面積が広くなったため。備中ぐわや千歯こきなど新しい農具で効率があがったため。
江戸時代に石高が増加した理由
①新田開発による農地の拡大と、②農業技術の向上による収穫量の増加が挙げられます。これらの取り組みにより、全国的に石高が増加し、江戸時代の経済と社会の安定を支える基盤となりました。
新田開発(しんでんかいはつ)
新しい田畑を開墾することで農地が増加したため、石高(米の収穫量)も増えました。江戸時代の安定した政治体制により、戦国時代のような戦乱がなくなり、人々が農業に集中できる環境が整いました。特に幕府や藩が積極的に新田開発を奨励し、湿地帯や荒地を田畑に変える事業が進められました。
例:干拓(海や湖を埋め立てて農地にする方法)や山林の開墾。
代表例:加賀藩の木曽川下流域の新田や、九州の有明海沿岸の干拓。
農業技術の向上
農業技術の進歩により、既存の田畑の収穫量が増加したためです。品種改良や農具の発達、耕作方法の工夫が進み、同じ面積の農地からより多くの米が取れるようになりました。
戦乱の終結による安定した社会
戦国時代には、戦乱や領地争いで農地が荒廃していましたが、江戸時代には戦争がなくなり、平和な時代が続きました。社会が安定したことで農業に集中できる環境が整い、新しい農地を開発する余裕が生まれました。また、大名や幕府が長期的な領地経営を目指すようになり、新田開発が奨励されました。
農具の改良
備中鍬(びっちゅうぐわ)
重い土壌を効率的に耕せる鍬が開発され、開墾作業や耕作が楽になりました。
湿地や粘土質の土地でも容易に農地化できるようになり、新田開発を促進しました。
千歯扱き(せんばこき)
稲の脱穀を効率化するための道具。歯の付いた板で稲を扱き、穂から籾を外す作業を簡単にしました。
唐箕(とうみ)
籾や殻を分離するための風力を利用した道具。これにより、選別作業が迅速かつ正確になりました。
金銀が国外に流出するのを防ぐため。
大量の金銀流出を防ぐため
江戸時代の貿易では、日本から金や銀が主要な輸出品として取引されていました。特に金銀は高い価値を持ち、日本の埋蔵量も限られていたため、大量に海外に流出することが国内経済に悪影響を及ぼしていました。新井白石は、貴重な金銀が流出し続けることで、日本の経済基盤が弱体化することを懸念し、貿易額を制限して流出を抑えようとしました。
新井白石(あらい はくせき、1657年~1725年)
江戸時代中期の儒学者、政治家、歴史家であり、江戸幕府の政策に大きな影響を与えた人物です。特に6代将軍徳川家宣(いえのぶ)と7代将軍徳川家継(いえつぐ)の時代に幕政を補佐し、改革を推進しました。その学問的業績と政治的功績により、江戸時代の有力な知識人の一人として知られています。
主な業績
①正徳の治(しょうとくのち)
家宣と家継の時代に実施された一連の改革政策を指します。倹約令の実施や金銀流出を防ぐための貿易制限が代表的です。
②金銀流出防止策
長崎貿易における金銀流出を防ぐため、貿易額や外国船の来航数を制限しました。
③貨幣改鋳
質の悪かった貨幣(元禄金銀)を改鋳し、経済の安定を目指しました。
かいこのえさであるくわの栽培が盛んになった。
享保の改革(1716年~1745年)
8代将軍徳川吉宗が幕府の財政を立て直すため、農業や産業の振興を推進しました。この中で生糸(きいと)の増産が奨励されました。
生糸の輸出の活発化
日本産の生糸は高品質であり、中国やヨーロッパ諸国で需要が高かったため、輸出が活発化しました。特に、長崎貿易を通じてオランダや中国への生糸の輸出が増え、日本の貿易収入が増加しました。生糸は幕府や藩にとって重要な外貨(銀)獲得の手段となり、財政安定に貢献しました。
養蚕業の仕組みと生糸生産
養蚕業は、蚕(かいこ)を飼育して繭(まゆ)を作らせ、そこから生糸を取るという仕組みです。農村では、農民が桑(くわ)の木を栽培し、その葉を蚕のエサにすることで養蚕が行われました。繭から生糸を取る作業は、農民の手仕事として副業的に行われ、簡易な設備で始められるため普及が進みました。
日本産の生糸が高品質と評価された
①気候や地理条件に恵まれていたこと
②蚕の飼育や製糸技術が高度だったこと
③品質管理が徹底されていたこと
この高品質な生糸は、国内外での需要を高め、日本の経済や国際貿易の発展を支える重要な役割を果たしました。
【享保の改革の内容】
①倹約令の実施
武家や幕府役人に倹約を命じ、贅沢を控えることで幕府の支出を抑えました。衣服、贈答品、宴会などの節約が推奨されました。
②上米の制(あげまいのせい)
大名に対し、石高1万石につき100石の米を幕府に納めるよう命じました。
代わりに、大名の参勤交代の期間を緩和し、負担を軽減しました。
③貨幣の改鋳(かいちゅう)
幕府は貨幣を改鋳し、金や銀の含有量を調整して貨幣の価値を安定させました。
④目安箱の設置
江戸城内に目安箱を設置し、庶民から意見や苦情を集めました。これにより、民衆の声を政策に反映させる仕組みが作られました。
⑤公事方御定書(くじがたおさだめがき)の編纂
裁判や行政の基準となる法律書を整備し、公平な裁判を実現しました。
農民をひとつの場所に集めて、作業を分担させることで製品を作る生産体制のこと。
工場制手工業(こうじょうせいしゅこうぎょう)
同じ場所(工場)に多くの職人や労働者を集めて、分業によって製品を生産する方法のことを指します。これは、従来の農家や家内で行われていた小規模な手工業(家内制手工業)から発展した生産体制です。
制手?
「制手」は特定の言葉ではなく、「工場制」と「手工業」が組み合わさったものです。これは、手作業による工業生産を、工場という組織化された場で行う生産方式を指しており、江戸時代後期から明治時代初期にかけて発展しました。この方式は、後の工場制機械工業(機械を用いた大量生産)への橋渡しとなる重要な生産形態でした。
【家内制手工業と工場制手工業の比較】
| 項目 | 家内制手工業 | 工場制手工業 |
|---|---|---|
| 生産場所 | 家庭(自宅) | 工場(集中的な作業場) |
| 生産規模 | 小規模 | 大規模 |
| 分業の有無 | なし(全工程を一人または家族が担当) | あり(作業を分担して効率化) |
| 管理者の存在 | いない | いる(工場経営者や監督者が管理) |
| 目的 | 自給的、または小規模な市場販売 | 市場販売を前提とした大量生産 |
| 労働形態 | 家族経営や副業的 | 賃金労働者による専業化 |
政治批判の禁止、出版内容の制限など統制が厳しかったこと。
政治批判の防止
幕府の威厳を保つため、松平定信は政治批判を厳しく取り締まりました。具体的には、幕府の政策や権威を批判する書物や情報が広まることを防ぐため、出版物に対して厳しい監視を行いました。政治を批判する内容が含まれると判断された場合、出版は禁止され、時には処罰が科されることもありました。
出版内容の統制
政治批判だけでなく、幕府の秩序や道徳に反すると見なされる出版内容も制限されました。例:歴史書や小説などで、幕府に不都合な記述や不道徳とされる内容が含まれる場合、出版が禁止されました。また、政治的に中立でない内容や、庶民に奢侈や反乱を助長するとみなされる内容も厳しく取り締まりの対象となりました。
思想や文化の統制
松平定信は、朱子学を正統な学問として推奨し、他の思想や学問を抑制しました。
出版物の検閲を通じて、多様な思想の流布を防ぎ、社会の秩序を維持しようとしましたが、これが知識人や学者たちの反発を招きました。同時に、庶民や商人が享受していた娯楽や文化も、出版物の制限によって抑えられる結果となり、不満が高まりました。
統制を厳しくした理由
松平定信が統制を厳しくしたのは、①幕府の権威を守るため、②社会秩序を回復するため、③天災や経済危機に備えるため、④民衆の不満を抑えるためでした。当時の江戸幕府は、多くの問題に直面しており、改革を通じて社会の安定を図る必要がありました。しかし、厳しい統制は民衆や商人、知識人の不満を招き、改革全体の成果が限定的なものになる要因にもなりました。
寛政の改革(1787年~1793年)
老中松平定信が幕府の財政難や社会の混乱を立て直すために行った改革です。
①財政再建
武士や庶民に倹約を命じ、幕府の支出を減らす。米を備蓄する制度を実施。
②農村の安定
新田開発を奨励して農地を拡大。借金の帳消しを発令し、農民の負担を軽減。
③思想と出版の統制
朱子学を正統な学問として推奨し、他の学問や批判的な出版物を制限。幕府への批判を防ぎ、社会秩序を保とうとした。
④民衆の声を反映
江戸城に目安箱を設置し、庶民からの意見を募る。
松平定信
厳格で質素な人物であり、幕府の再建を目指して寛政の改革を主導した政治家です。享年は71歳で、朱子学を重んじた道徳的な社会の実現を目指しました。主な実績として、倹約令や囲米、目安箱の設置が挙げられますが、その厳しい政策は民衆や商人に不満を招き、改革の成功は限定的でした。それでも、彼の姿勢は江戸時代の重要な政治的遺産として評価されています。
朱子学とは
儒教の一派であり、朱熹(しゅき)がまとめた道徳や社会秩序を説く学問。上下関係や家庭、社会の秩序を重視し、特に徳を高めることを教える。武士を含む多くの階層で学問として重視され、江戸幕府も社会秩序の安定に利用した。人としての道徳や社会の秩序を守ることで、平和な社会を築くことを目的としました。江戸時代における教育や政治思想に大きく影響を与えた。
凶作やききんに備えるため。
囲い米
寛政の改革で倉を設けて米を蓄えさせた政策は、囲米(かこいまい)と呼ばれました。この政策の目的は、飢饉への備えと米価の安定を図ることにありました。
飢饉(ききん)への備え
江戸時代の天明年間(1782年~1787年)、日本を襲った天明の飢饉では、多くの農作物が実らず、全国で多数の餓死者が出ました。食料が不足した農民や都市住民は大変な苦しみに直面し、その不満は次第に一揆や暴動といった形で表れ、社会の安定を脅かす大きな問題となりました。
この危機的な状況を教訓に、寛政の改革を主導した松平定信は、飢饉に備えて食糧を蓄える囲米政策を実施しました。幕府は大名や農村に対し、専用の倉を設け、一定量の米を備蓄するように命じました。各地で倉に蓄えられた米は、不作や飢饉が再び起こった際に放出され、食料不足を補う役割を果たす仕組みです。
この政策により、飢饉が発生しても蓄えた米を供給することで被害を軽減し、社会不安の広がりを防ごうとしました。囲米政策は、天明の飢饉のような大規模な被害を防ぐための重要な備えとして実施されたのです。
飢饉と改革
①正徳の治(1716年~1719年)
江戸時代前期は冷害や小規模な飢饉が度々発生し、農村が疲弊していました。また、元禄時代の贅沢な政策で財政が悪化し、幕府再建のための改革が必要でした。新井白石の指導で、農村整備や財政の健全化を目指しました。
②享保の改革(1716年~1745年)
改革の途中で享保の飢饉(1732年)が発生し、米の不足や価格高騰が深刻な問題となりました。徳川吉宗は農業を重視し、新田開発や農書の普及などの政策を行い、飢饉への対応を図りました。
③天保の改革(1841年~1843年)
天保の飢饉(1833年~1839年)の影響で社会不安が広がり、一揆や暴動(大塩平八郎の乱など)が相次ぎました。水野忠邦は飢饉対策や財政再建を目指し、米価の安定や人返しの法などの政策を実施しましたが、短期間で終了しました。
アヘン戦争で清がイギリスに負けたこと。水、食料、燃料などを調達することに限り入港を認める内容に変更。
異国船打払令の概要
制定時期:1825年(文政8年)日本近海に接近した外国船(特に西洋船)を、理由を問わず攻撃して追い払うよう命じた政策。鎖国体制を守り、外国の侵略や影響を排除すること。特に、イギリスやアメリカなどの西洋諸国の接近を警戒していました。
内容変更が行われた背景
アヘン戦争の影響(1839年~1842年)清(中国)がイギリスに敗北し、1842年に南京条約を締結したことで、イギリスがアジアへの影響力を強めた。幕府は清の敗北を目の当たりにし、日本も同様の脅威にさらされる可能性があると判断しました。外国船が日本に頻繁に接近し、薪(たきぎ)や水、食料を求めるケースが増加していました。無条件で追い払うと、国際紛争を招く恐れが高まりました。
変更内容:天保の薪水給与令(しんすいきゅうよれい)の発布
外国船が日本に接近した際に、食料や水、薪を要求してきた場合、武力で追い払うのではなく、必要最低限の補給を許可するように変更しました。ただし、これ以上の接触や長期滞在は認められず、あくまで一時的な対応としました。
天保の薪水給与令の影響
異国船打払令の変更により、日本近海に接近する外国船との衝突は一時的に減少しました。しかし、この柔軟な対応は幕府の外交政策の転換点となり、後に1853年のペリー来航や1854年の日米和親条約へとつながる、開国への第一歩とも言えます。
なぜそこまでビビった?
アヘン戦争(1839年~1842年)では、当時のアジア最強国とされていた清が、イギリスの軍事力に大敗しました。清は大きな譲歩を強いられました。イギリスに有利な貿易条件の受け入れ(関税自主権の喪失)。これを見た日本は、同じアジア諸国として、「自分たちも西洋列強に屈する可能性がある」と強く意識しました。
幕府は清の敗北を見て、「軍事力や外交力が不足すれば、同じように列強に屈服し、主権を失う危険がある」と考えました。
鎖国→開国の流れ
| 年号 | 出来事 | 内容と背景 |
|---|---|---|
| 1639年 | 鎖国の完成 | ポルトガル船の来航を禁止し、オランダ、中国、朝鮮、琉球など一部の国との貿易を限定的に許可。 |
| 1825年 | 異国船打払令の発布 | 西洋列強の接近を警戒し、日本近海に現れた外国船を理由を問わず追い払うよう命じた。特にイギリスやアメリカ船を警戒。 |
| 1839年~1842年 | アヘン戦争 | 清(中国)がイギリスに敗北。南京条約で領土割譲や不平等条約を結び、アジア諸国に列強の脅威が広まる。 |
| 1842年 | 異国船打払令の内容変更 | アヘン戦争を見た幕府が対応を変更。外国船に薪や水、食料を求められた場合、補給を認めて衝突を避ける方針に転換。 |
| 1853年 | ペリー来航 | アメリカのペリー艦隊が浦賀に来航し、日本に開国を要求。幕府は鎖国政策の転換を迫られる。 |
列強の軍事力に対抗するため。
大砲を製造した目的
外国からの軍事的な脅威に備えるためでした。ペリー来航をはじめとする西洋列強の圧力に対し、日本全体が防衛力の強化を迫られました。また、反射炉を用いた大砲製造は、各藩が西洋技術を積極的に取り入れ、自主的に軍備を整える動きの一環でもありました。
列強(れっきょう)とは
軍事力や経済力が強く、国際的に大きな影響力を持つ国々のことを指します。特に近代以降、西洋諸国を中心に使用されることが多い言葉です。
19世紀(江戸時代末期)の列強
①イギリス:産業革命の中心国で、海軍力と経済力が圧倒的。広大な植民地を支配。
②フランス:ヨーロッパの主要国で、文化や政治的影響力も大きい。
③アメリカ:急速に発展して列強の仲間入りを果たした国。
④ロシア:広大な領土と軍事力を持つ。
⑤オランダ:日本との貿易で知られるが、19世紀には他の列強に比べ影響力が低下。
反射炉(はんしゃろ)
鉄を溶かして鋳造(ちゅうぞう)するための高温の炉(溶解炉)です。鉄を高温で溶かし、大砲やその他の金属製品を製造するために使用されました。江戸時代末期、日本が西洋技術を取り入れながら防衛力を強化する過程で建設されました。主に沿岸部や軍事拠点に建設されました。短期的には日本の防衛力をある程度強化しましたが、外国の圧倒的な軍事力との差を埋めるには限界がありました。しかし、その技術や経験は明治以降の日本の近代化に大きな影響を与え、結果的に反射炉は近代日本の産業基盤を築く出発点として重要な役割を果たしたと言えます。
アメリカからペリーが黒船で来航したこと。
この狂歌「泰平の眠りを覚ます上喜撰 たった四杯で夜も眠れず」は、ペリー来航(1853年)を皮肉った内容のものです。ペリー来航をきっかけに、日本が鎖国から開国を迫られ、長い平和が揺らぎ始めた状況を風刺したものです。黒船(蒸気船)がもたらした衝撃を、江戸時代の文化的背景を活かしながら巧みに表現しています。この出来事は、日本が近代化へと進む大きな転換点となりました。
狂歌の意味
「泰平の眠り」江戸幕府が約200年間にわたって維持してきた平和で安定した社会を指します。鎖国政策により外国との接触を最小限にし、国内の秩序を守ってきた日本の状況を表現しています。
「上喜撰(じょうきせん)」実際には高級なお茶の銘柄を指しますが、この狂歌では「蒸気船(じょうきせん)」にかけた洒落です。黒船が蒸気の力で動く船だったことを指し、「上喜撰」として描写されています。
「たった四杯で夜も眠れず」ペリー艦隊の4隻の黒船が、平和な日本を驚かせ、幕府や人々が動揺して眠れなくなった様子を表現しています。
狂歌(きょうか)とは
五七五七七の和歌の形式を基にしながら、内容をユーモラスや皮肉を込めた風刺的なものにした詩のことです。江戸時代に特に流行し、庶民の間で親しまれました。社会や風俗、時事問題などを題材に、軽妙な言葉遊びや洒落を用いるのが特徴です。
その他の有名な狂歌
「白河の清きに魚も住みかねて 元の濁りの田沼恋しき」
田沼意次(たぬまおきつぐ)の政治と松平定信の政治を比較した狂歌。
①田沼時代(濁り):贅沢や賄賂が横行したが、経済が活発で庶民が恩恵を受けた。
②松平定信の時代(清き):質素倹約を強いたため、庶民が生活の苦しさを嘆いた。
清く正しい政治を行う松平定信よりも、田沼意次のような賑やかで活気のある政治のほうがよかったという皮肉。
日本がアメリカから製品を輸入するとき、関税率を決める関税自主権がないこと。
日本で罪を犯したアメリカ人を日本の法律で裁くことができない領事裁判権をアメリカに認めていたこと。
井伊直弼(1815年~1860年)
幕末の江戸幕府の大老で、日米修好通商条約の締結や安政の大獄を主導した人物です。外国からの圧力に対応するため、1858年に天皇の許可を得ないまま条約を締結し、日本を開国へ導きました。しかし、不平等条約や反対派弾圧への反発を招き、1860年には桜田門外の変で暗殺されました。井伊直弼は、幕末の混乱期に現実的な判断を下し、近代日本への道を切り開いた政治家として知られています。
関税自主権の欠如
輸出入品にかかる関税率を、日本が自由に決めることができず、アメリカなどの外国と協議して決定する仕組みになりました。日本の経済政策における主権が制限されることを意味します。日本は、関税で輸入品を制限したり、自国の産業を保護することができませんでした。そのため、外国からの安価な商品が大量に流入し、日本の経済に混乱をもたらしました。
関税自主権が無いと・・・
例:パン屋さんの話
ある町にパン屋さんがたくさんあります。その町に「外国から安いパン」がたくさん届きました。外国のパンはすごく安いので、みんなそのパンを買い始めて、町のパン屋さんはお客さんが減って困ってしまいました。普通なら、この町のルールで「外国のパンに税金をかける」ことで、値段を少し高くして、町のパン屋さんを守ることができます。でも、関税自主権がないと、そのルールを外国と相談しなければならず、「外国のパンに税金をかけてはいけない」と言われてしまうことがあります。関税自主権がないと、外国と公平に貿易ができなくなり、日本の商品や働く人たちが困ることになります。自分たちのルールを自分で決められないのは、とても不利なことです。
領事裁判権(治外法権)の承認
日本国内で犯罪を犯した外国人は、日本の法律で裁かれるのではなく、その外国の領事が自国の法律で裁くことが定められました。これは日本の司法権が制限される形となり、外国人に特別な地位を認めるものです。日本の主権が侵害され、不平等条約の象徴とされました。この領事裁判権の問題は、明治政府が条約改正を目指す大きな理由の一つとなりました。
領事裁判権を認めてしまうと・・・
例:外国人が日本で殺人を犯したら
ある外国人が日本で悪いことをして、人を殺してしまいました。普通なら、日本で起きた事件なので、日本の警察が捜査をして、日本の法律で裁かれるべきです。しかし、領事裁判権があると、その外国人は日本ではなく、自分の国の法律で裁かれることになります。(例:日本で人を殺しても、その外国では罪が軽い場合があります。)その裁判は、日本ではなく外国の領事館が行うため、日本人の立場や被害者のことが十分考慮されない可能性があります。
日米修好通商条約が結ばれる流れ
①ペリー来航と開国の圧力
1853年:アメリカのペリー提督が浦賀に来航し、鎖国を解いて開国するよう求めました。幕府は強い軍事力を背景にした要求に対応せざるを得ず、即座に決定を避けて翌年の再来航を求めました。1854年ペリーが再来航し、幕府は妥協して日米和親条約を結びました。この条約により、日本は下田と函館を開港し、燃料や食料などを外国船に提供することを認めました。ただし、この時点では本格的な通商は認められていませんでした。
②通商条約交渉の開始
アメリカをはじめとする西洋諸国は、日本に本格的な貿易を求めて交渉を続けました。特に、清国がアヘン戦争で敗北して開港を強制された状況を見て、日本も同様の圧力にさらされる可能性が高まっていました。ハリスの来日(1856年)アメリカ総領事ハリスが下田に着任し、日本に通商条約を締結するよう強く求めました。ハリスは、日本が開国を拒む場合、武力行使の可能性を示唆しました。
③幕府内の混乱と条約交渉の進展
ハリスとの交渉は進みましたが、幕府は条約締結について朝廷(天皇)の許可を求めるべきかどうかで迷いました。鎖国政策の伝統を守りたい一部の勢力と、現実的な対応を取るべきだとする勢力が対立。幕府は条約の草案を朝廷に提出しましたが、朝廷は鎖国を続けることを望み、許可を与えませんでした。
④井伊直弼の判断
大老就任(1858年)井伊直弼は、幕府の最高実力者である大老に就任しました。この時期、幕府の権威は低下しており、国内外の課題に対応する必要がありました。1858年、井伊直弼は天皇の許可を得ないまま、アメリカとの日米修好通商条約を締結しました。井伊は「開国を拒否すれば外国の武力介入を招く」と判断し、現実的な対応を優先したのです。
⑤条約締結後の影響
日本はアメリカに港を開き、貿易を開始。関税自主権の欠如や領事裁判権の承認といった不平等な条件が含まれていました。天皇の許可を得ずに条約を締結したことが、攘夷派(外国を排除すべきと考える勢力)の強い反発を招きました。この反発が激化し、1860年に井伊直弼が暗殺される(桜田門外の変)きっかけとなりました。
安政の大獄(あんせいのたいごく)とは
1858年から1859年にかけて、大老・井伊直弼(いいなおすけ)が攘夷派(外国を排除しようとする勢力)や条約反対派を厳しく取り締まった事件です。簡単に言うと、幕府に反対する人々を弾圧した出来事です。有名な志士たちを処罰、吉田松陰(よしだしょういん):萩(はぎ)の思想家。死刑。政治的に反対派を抑え込むことに成功しましたが、弾圧が厳しすぎたために反発がさらに強まりました。
吉田松陰(よしだしょういん)
江戸時代の最後のころに活躍した、日本を良くしようと考えたすごい学者で先生です。彼は新しい考え方をたくさん持ち、たくさんの弟子を育てました。ペリーの黒船が来たとき、松陰は「外国をもっと知りたい!」と思って、こっそり船に乗ろうとしました。でも失敗して、幕府に捕まってしまいました。松陰の弟子には、幕末の大改革を進めたリーダーの一人、高杉晋作(たかすぎしんさく)や日本の初代内閣総理大臣になった伊藤博文(いとうひろぶみ)など、日本を変えた人たちがたくさんいます。吉田松陰は、「日本をもっと良くしよう」と熱心に考えた学者で、多くの弟子を育てました。自分の夢のために全力で行動したすごい先生です。彼の考えや教えは、今でもたくさんの人に尊敬されています。
国外に金の流出を防ぐため、金の含有量が少なく、軽かった。
万延小判は、金の含有量が減らされ、軽量化された特徴を持つ小判です。発行の背景には、外国との貿易による金流出を防ぐ目的がありましたが、その結果、国内ではインフレーションが起きるなど、経済混乱を招きました。この出来事は、幕府の衰退と幕末の混乱を象徴する一例とされています。
金の含有量が少ない
それまで流通していた天保小判に比べ、万延小判は金の含有量が約57%に減らされました。金の量が減らされた理由は、外国との貿易で金が大量に海外へ流出してしまったためです。
軽量化
金の含有量が減らされた結果、重さも軽くなっています。これにより、国内では金貨の信用が低下しました。
見た目はほとんど同じ
万延小判は、見た目のデザインは従来の小判とほとんど変わりませんでした。しかし、中身の金の量が減ったことで、実質的な価値が大幅に下がりました。
幕府の工夫
幕末の日本では、外国と貿易をするようになったことで、日本のお金(小判)に含まれる金がたくさん外国に流れてしまいました。日本の金貨は外国のものより金が多く含まれていて価値が高かったので、外国商人が日本で安く手に入れて、自分の国で高く売っていたのです。
金がたくさん流出すると、日本の中でお金が足りなくなり、物の値段が上がって生活が苦しくなったり、国の経済が混乱したりしてしまいます。さらに、金が減ると幕府の財政も苦しくなり、国としての力も弱くなってしまうと考えられました。
そこで幕府は、金が流出しないように万延小判という新しいお金を作り、金の量を少なくしました。これによって外国商人が日本の金貨を狙う理由を減らそうとしたのです。しかし、この対策によって国内で物価が上がり、みんなの生活が大変になるという問題も起きました。
つまり、幕府は日本の金を守って国の経済を安定させるために、いろいろと工夫していたのです。
江戸時代の小判
| 小判の種類 | 発行時期 | 金の保有量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 慶長小判 | 1601年~ | 金の保有量が最も多い | 江戸幕府最初の小判。高品質で信頼性が高く、安定した貨幣として広く流通した。 |
| 元禄小判 | 1695年~ | 金の保有量が減少 | 幕府の財政難により金の含有量を減少。貨幣価値が下がり、庶民の不満を招いた。 |
| 正徳小判 | 1714年~ | 金の保有量が増加(回復) | 元禄小判の問題を受け、金の含有量を慶長小判に近づけた。貨幣の信用回復を目的とした。 |
| 万延小判 | 1860年~ | 金の保有量が約57%(最少) | 外国貿易での金流出を防ぐため、金の含有量を大幅に削減。国内ではインフレを引き起こし混乱を招いた。 |
アメリカで南北戦争がおこり、日本とアメリカの貿易の割合が小さくなった。
1865年ごろの日本とアメリカの貿易は、アメリカで南北戦争(1861年~1865年)が起きたことが大きな影響を与えました。この戦争により、アメリカは国内が分裂して経済や物流が混乱し、日本との貿易が減少しました。そのため、日本の貿易相手としてのアメリカの割合が小さくなりました。
南北戦争の影響
アメリカでは南部と北部が対立して戦争になり、国内の経済活動が戦争に集中しました。その結果、アメリカは日本との貿易に割く力が減り、輸出入が大幅に減少しました。
他国との貿易の拡大
アメリカとの貿易が減った分、日本はイギリスやフランスなど、他のヨーロッパ諸国との貿易を増やしました。特に、生糸や茶などの日本の商品はヨーロッパで人気があり、これらの国が新たな主要貿易相手となりました。
日本とアメリカの貿易の割合が小さくなった理由
南北戦争でアメリカが日本との貿易に力を入れられなくなった。日本はイギリスやフランスといった他の国との貿易を増やした。
南北戦争(1861年~1865年)
アメリカで北部と南部が戦った内戦で、主に奴隷制度をめぐる対立や国の進む方向の違いが原因でした。北部は工業を発展させ、奴隷制度に反対していた一方、南部は農業を中心に奴隷制度を守ろうとしました。1861年、南部がアメリカから独立を宣言して戦争が始まりましたが、1865年に北部が勝利して奴隷制度は廃止され、アメリカは再び1つの国となりました。この戦争によって「自由と平等」の考えが進みましたが、南北の対立はしばらく残りました。
新政権の中で政治の実権を握ることを目的に、幕府が朝廷に政権を返上すること。
大政奉還(たいせいほうかん)とは
江戸幕府の第15代将軍・徳川慶喜(とくがわよしのぶ)が、1867年に幕府の政治の権力(政権)を朝廷に返した出来事です。これは、幕府が自らの力を失いつつある中で、新しい時代の流れに対応しつつ、徳川家が新しい政権の中でも主導的な役割を担うことを目的として行われました。
徳川慶喜が政権を返上
1867年10月14日、徳川慶喜は朝廷に「政治を任せる」と申し出て、260年以上続いた江戸幕府の統治が終わることになりました。
大名たちに対する働きかけ
幕府は、大政奉還によって徳川家が「朝廷の新しい政権の一部として参加する」ことを示し、大名たちからの支持を得ようとしました。
結果
政権を朝廷に返したことで、形式的には幕府の時代が終わりを迎えました。しかし、薩摩藩や長州藩を中心とする倒幕派は「徳川家が新しい政権で主導権を握ること」を認めず、翌年の戊辰戦争へとつながります。
なぜ幕府は弱まっていたのか
江戸幕府が力を失ったのは、国内での経済問題や社会の変化が進む一方、外国の圧力(ペリー来航)による開国や不平等条約の締結(日米修好通商条約)が原因となり、人々が幕府の統治に不満を抱くようになったからです。これらの要因が重なり、幕府の権威は衰えていき、最終的に倒幕運動が成功して明治時代へとつながりました。
大政奉還から幕府滅亡の流れ
大政奉還(1867年10月14日)は、徳川慶喜が朝廷に政権を返上し、平和的に新しい政治体制を作ることで、徳川家が新政府の中でも影響力を保とうとした試みでした。しかし、これに納得しなかった薩摩藩や長州藩を中心とする倒幕派は、同年12月9日に王政復古の大号令を発し、「天皇中心の新政府の樹立」と「徳川家を政治から排除すること」を宣言しました。この動きにより、徳川家は新しい政治体制から排除されることとなり、慶喜は反発しました。そして、1868年1月に起きた鳥羽・伏見の戦いをきっかけに、徳川家と倒幕派の間で戊辰戦争が勃発し、最終的に徳川家は敗北。江戸幕府は完全に滅亡し、日本は天皇を中心とした明治政府へと移行しました。この一連の流れは、平和的な権力移行を目指した大政奉還が、最終的に武力衝突へとつながり、幕府の時代が終わる結果を生んだことを示しています。
一揆の中心人物をわからなくするため。
からかさ連判状とは
一揆を計画する際、参加者たちが署名する誓約書のことです。署名をすることで、一揆に参加する意思を示しました。名前の由来は、署名の配置が傘(からかさ)の骨のような形をしていることにちなんでいます。署名を円形に並べることで、誰が最初に署名したのか(つまり一揆のリーダー)がわからないようにしました。幕府や藩が一揆の中心人物を捕まえようとしても、署名の順番が特定できないため、責任を追及しにくくなる工夫です。
からかさ連判状が使われた時代
江戸時代(1603年~1868年)江戸時代は約260年の平和な時代でしたが、その間に農民の生活が厳しくなり、一揆が増えていきました。特に18世紀後半から19世紀(1700年代後半から1800年代)にかけて、凶作や重い年貢、物価の上昇が原因で、多くの一揆が起こるようになりました。
この時代の一揆の特徴
(1) 百姓一揆
原因重い年貢や、飢饉(ききん)による農村の困窮。地主や役人の不正。
特徴村全体が団結して不満を訴えることが多かった。年貢の減免や食糧の供給を要求することが主でした。からかさ連判状は、この百姓一揆で広く使われました。
(2) 打ちこわし
原因都市部での米や生活必需品の値上がり。
特徴農村ではなく、町人が中心。米問屋や裕福な商人の家を襲い、物を壊したり奪ったりする暴動が起きました。
(3) 世直し一揆
原因幕末の社会不安や経済の混乱。新しい時代を求める民衆の声。
特徴単に年貢の軽減を求めるだけでなく、「社会そのものを変えたい」という願いを込めた大規模な一揆。
外国勢力を排除しようとする考え方。
攘夷論は外国勢力を排除して日本を守るという考え方であり、これが天皇を中心とした国づくりを目指す尊王攘夷運動へと発展し、その挫折を経て幕府を倒し開国・近代化を進める明治維新へとつながりました。
攘夷論の主な内容
外国を追い払うべきだという主張。外国船の撃退や通商条約の破棄を求める声が高まりました。特に、武士や尊皇派(天皇を重んじる人々)が中心となり、「日本を守るために外国を排除するべき」と考えました。攘夷論者は、「天皇を中心に国を守るべきだ」と主張し、後の尊王攘夷運動へとつながります。
攘夷論の展開
幕府も一時的に攘夷論を取り入れ、1863年に「攘夷実行の命令」を出しました。しかし、実際には外国の軍事力に対抗できず、失敗に終わりました。攘夷論は現実的には外国の力に対抗できないことが明らかになり、次第に開国・近代化を進める考え方(倒幕運動や明治維新)へと変わっていきました。
攘夷論で有名な人
吉田松陰(よしだしょういん)幕末の思想家で、外国勢力を排除し、日本を守るための攘夷を強く主張しました。開国の必要性を認めつつも、日本が独自の力をつける前に外国に屈することを避けようとしました。多くの弟子を育て、明治維新のリーダーたちに影響を与えました。
攘夷論に敵対する勢力で有名な人
井伊直弼(いいなおすけ)幕府の大老として、1858年に日米修好通商条約を締結し、開国を進めました。外国の圧力に現実的に対応し、開国を選択しましたが、攘夷論者や反対派を弾圧(安政の大獄)したことで強い反発を招き、1860年の桜田門外の変で暗殺されました。
吉田松陰は「攘夷」を掲げて外国を排除することを目指し、井伊直弼は「現実的な開国」を選択する立場でした。この対立は幕末の大きな争点となり、日本の進む道を大きく変える要因となりました。
明治
ひとりの天皇の在位中は、ひとつの元号のみを用いる制度。
一世一元の制(いっせいいちげんのせい)
ひとりの天皇が在位している間、元号をひとつだけに固定する制度のことです。天皇が崩御(亡くなる)したり、退位した場合にのみ、新しい元号が定められます。この制度は、1868年(明治元年)から始まりました。明治天皇の時代に「明治」という元号が定められ、天皇の崩御まで続きました。明治政府は、天皇を中心とした安定した国家を目指し、「一世一元の制」を導入することで、国民に統一感と秩序を与えようとしました。
明治以降の元号
明治、大正、昭和、平成、令和の5つです。それぞれの元号が天皇と結びつき、日本の歴史を象徴しています。一世一元の制により、天皇ごとに元号が統一されていることが特徴です。
明治天皇(めいじてんのう)
明治時代(1868年~1912年)は、日本が近代国家として改革を進めた時期。明治維新を実現し、富国強兵や文明開化を進めました。
大正天皇(たいしょうてんのう)
大正時代(1912年~1926年)は、短い期間ながらも大正デモクラシーなど、民主主義が進展した時代。
昭和天皇(しょうわてんのう)
昭和時代(1926年~1989年)は、日本が戦争、敗戦、復興を経験した激動の時代。戦後の平和と経済成長が特徴的。
平成天皇(へいせいてんのう/明仁天皇)
平成時代(1989年~2019年)は、バブル崩壊や災害が多発する中で、国際協力と平和を重視した時代。
令和天皇(れいわてんのう/徳仁天皇)
令和時代(2019年~現在)は、令和という元号に「人々が美しく心を寄せ合う平和な時代」という願いが込められています。
牛肉を食べることが広まった。
文明開化の時期に牛肉を食べることが広まったのは、西洋の食文化を取り入れて近代化を目指したからです。この変化は、日本の食生活における大きな転換点となり、現代の食文化の基盤を築きました。
牛肉を食べるようになった背景
明治時代になるまで、日本では仏教の影響で肉食があまり行われていませんでした(四つ足の動物を食べることが避けられていました)。しかし、西洋から「牛肉は健康に良い」「体力がつく」という考え方が伝わり、肉食が推奨されるようになりました。明治天皇が「牛肉を食べた」という話が広まったことで、牛肉を食べることが一般の人々にも受け入れられるきっかけとなりました。西洋文化を取り入れることが進歩的だと考えられ、牛鍋(現在のすき焼き)が都市部を中心に人気を集めました。
文明開化(ぶんめいかいか)とは
明治時代に日本は「もっと強い国になろう」と考え、西洋の文化や技術を取り入れて、暮らしや社会を変えていったことを言います。この時期、日本は「新しい時代」に向かって大きく変わりました。
どんなことが起きた
洋服や洋風の家
着物だけじゃなく、スーツのような洋服を着る人が増えました。西洋風のレンガ造りの建物や学校が作られるようになりました。
鉄道やガス灯
鉄道が作られて、電車での移動ができるようになりました。夜にはガス灯が街を明るく照らしました。
学校や教育
子どもが学校に行くことが義務になり、西洋の勉強を取り入れた教育が始まりました。
文明開化に関連するワード
| 重要語句 | 簡単な説明 |
|---|---|
| 文明開化 (ぶんめいかいか) | 明治時代に西洋の文化や技術を取り入れて、生活や社会を近代化したこと。 |
| 富国強兵 (ふこくきょうへい) | 国を豊かにして強い軍隊を作る政策。文明開化もその一環として進められた。 |
| 殖産興業 (しょくさんこうぎょう) | 産業を発展させるために、西洋の技術や工場を取り入れた政策。産業革命の基盤となった。 |
| 鉄道 | 日本初の鉄道は1872年に新橋(東京)~横浜間で開通し、文明開化の象徴となった。 |
| 学制(がくせい) | 1872年に作られた学校制度で、すべての子どもが学校に通うことを目指した。 |
| 郵便制度 | 1871年に始まった新しい通信制度で、文明開化によって広まった生活の変化のひとつ。 |
| 鹿鳴館 (ろくめいかん) | 明治政府が外国の人々をもてなすために建てた洋風建築。西洋化の象徴とされたが、一部では批判もあった。 |
| 文明開化の歌 | 「ハイカラな文化」を象徴する歌として「鹿鳴館で舞踏会」や「西洋かぶれ」というイメージが広まった歌。 |
中央から県令を派遣しておさめさせた。
明治政府は、廃藩置県を行い、全国を府と県に再編して、中央から派遣された県令が地方を治める仕組みを作りました。また、地租改正によって土地と税を管理し、人民を支配する中央集権的な体制を確立しました。この仕組みは、近代国家を作る基礎となりました。
県令の派遣
明治政府は、各府県に県令(後の知事)を派遣し、地方を統治させました。土地と人民を効率的に治めるために、県令は中央政府からの命令を実行する役割を担い、土地の管理や人民の支配、税の徴収を行いました。
中央集権体制の意義
藩ごとにバラバラだった統治を廃止し、中央からの指示で全国を一元的に管理することで、政府の力を地方にまで及ぼしました。これにより、富国強兵や殖産興業といった明治政府の改革を円滑に進める基盤が作られました。
廃藩置県(1871年)
それまでの藩を廃止し、全国を府と県に再編しました。これにより、藩主(大名)による地方の統治をやめ、すべての土地と人民を中央政府が直接管理するようにしました。
地租改正(1873年)
土地の所有者を明確にし、土地に対して地租(税金)を課す制度を作りました。地主から地租を徴収し、政府の財政を安定させました。
幕末に結ばれた不平等条約を改正するため。
岩倉使節団は、不平等条約の改正を目指し、さらに西洋の制度や技術を学ぶために派遣されました。条約改正は達成できませんでしたが、日本の近代化に向けた大きな成果をもたらしました。この使節団の活動は、明治維新後の日本の改革に大きな影響を与えています。
岩倉使節団派遣の目的
①不平等条約の改正
幕末に結ばれた日米修好通商条約(1858年)などでは、関税自主権の欠如や領事裁判権の承認など、日本に不利な内容が含まれていました。明治政府は、日本が独立した近代国家として認められるために、これらの不平等条約を改正しようとしました。
②西洋の文化や技術の学習
明治政府は、日本を近代化するために西洋の制度や技術を取り入れようとしていました。岩倉使節団は、ヨーロッパやアメリカを巡り、政治、経済、教育、産業などの仕組みを学び、日本に取り入れるべきものを調査しました。
岩倉使節団の概要
派遣時期1871年~1873年
団長岩倉具視(いわくらともみ)
メンバー木戸孝允、大久保利通、伊藤博文など
訪問国アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアなど約20カ国。
最初は男女の就学率の差は大きかったが、1910年時点ではほぼ同じになった。
学制は1872年に公布され、日本で初めて子どもたちが学校に通う仕組みが作られました。その後、1890年には教育の基本方針として教育勅語が発布され、道徳や忠孝の重要性が教えられるようになりました。また、福沢諭吉は「学問のすすめ」を通じて教育の大切さを広め、男女平等の教育を主張しました。一方、津田梅子は女子教育の先駆者として活躍し、帰国後に女子英学塾(現在の津田塾大学)を設立し、女性の学びの場を広げました。そして、明治政府のリーダーである伊藤博文は、日本の近代化政策を進める中で教育制度の整備に深く関与し、学制の実現や教育改革を支えました。
学制公布当初の状況
当時の日本では、「女子に教育は必要ない」と考える人が多く、男子に比べて女子の就学率は低い状況でした。学校に通える環境が整備されておらず、特に女子教育の普及は遅れていました。明治初期の社会では、男子が「将来の家族を支える存在」と見なされ、男子の教育が優先されました。一方で、女子は家事や育児を担う役割が期待され、教育の必要性が軽視されていました。
徐々に就学率の差が縮まった理由
明治政府が「女子にも教育が必要」と考えるようになり、女子のための学校が増えました。特に高等女学校の設置が進み、女子の就学率が上昇しました。1886年に義務教育期間が4年間と定められ、教育がより広く普及しました。その後、1907年に義務教育期間が6年間に延長され、男子も女子も学校に通う機会が増えました。
学制(がくせい)
明治時代に日本で初めて作られた学校の仕組みのことです。1872年に始まり、すべての子どもが学校に行けるようにするために作られました。
学制の具体的な内容
①すべての子どもが学校に通うこと
6歳以上の男女すべてが学校に通うことを義務化しました。小学校にあたる「初等教育」が重視され、読み書きや計算などの基礎教育が行われました。
②全国を8つの大学区に分けて管理
日本全国を8つの「大学区」に分け、その下に「中学区」や「小学区」を設置しました。学区ごとに学校を建て、子どもたちが通いやすくすることを目指しました。
③教育内容の近代化
教育の内容には、読み書きや算術(計算)だけでなく、地理や歴史、道徳が含まれていました。西洋式の教育を取り入れ、国の近代化を支える人材を育成することが目的でした。
地域の人々とのつながり
①学校建設に協力
学制の実施により、学校を建設するための費用や労働を地域の人々が分担しました。村ごとに協力して校舎を建てたり、教材を準備したりすることで、地域全体が教育に参加する仕組みができました。
②保護者の負担
初期のころは、学校に通うための費用(授業料)や必要な物資(教科書や文房具など)を保護者が負担する必要がありました。特に農村部では、「子どもを学校に通わせるよりも、家の仕事を手伝ってほしい」という考えが強く、就学率が低い地域もありました。
氏族と平民の区別なく、満20歳になった男子が兵役につくことになった。
徴兵令は、明治天皇のもとで進められた富国強兵政策の一環として1873年に公布され、武士中心の軍隊から国民皆兵の近代的な軍隊を作ることを目指しましたが、これに反対した西郷隆盛は、旧武士を中心とした軍隊の維持を主張し、後に西南戦争へとつながりました。
徴兵令における意義
徴兵令の下では、「武士(氏族)だけが戦う」という考えを廃止し、「すべての男子が国を守る責任を負う」という平等の理念が導入されました。これにより、氏族(旧武士)と平民(旧農民・町人)の区別なく、20歳以上の男子が兵役の対象となりました。
1873年以前と以後
| 項目 | 1873年以前 (武士中心の軍隊) | 1873年以後 (徴兵令公布後) |
|---|---|---|
| 軍隊の構成 | 主に武士が軍隊を構成 | 全国民が対象(20歳以上の男子が徴兵対象) |
| 役割と負担 | 武士が戦闘や治安維持を担う | 一般国民も兵役の義務を負う(国民皆兵) |
| 兵役の義務 | 武士の特権であり、農民や町人には軍務の義務はなかった | 20歳以上の男子に兵役を義務付けた(3年間の兵役、4年間の予備役) |
| 徴兵免除の仕組み | 免除という概念はなし | 代人料を支払うことで兵役を免除可能。病気や家庭事情による免除もあり。 |
| 目的 | 藩や幕府のために戦う | 近代的な国民軍を作り、富国強兵を実現する |
| 軍隊の規模 | 各藩ごとに異なり、全国規模の統一的な軍隊はなかった | 全国規模で統一された軍隊が形成され、中央集権的な軍事体制が確立された |
| 社会の反応 | 武士にとっては特権であり、農民や町人にとっては無関係 | 農民や庶民の間で「兵役への不満」から徴兵反対一揆が起こることもあった |
税収を安定させるため、土地の所有者は地価の3%を現金でおさめること。
地租改正では、江戸時代の年貢に代わり、土地の価値である地価を基準に計算された税を地券を持つ土地所有者が現金で納める仕組みを導入し、政府は安定した財源を確保して富国強兵を進めました。
地租改正の内容
土地の所有者が納税の義務を負うようになりました。それまでは、土地を耕している農民が米で年貢を納めていましたが、地租改正によって土地所有者が現金で納税する仕組みに変わりました。税金は、土地の価値(地価)の3%を基準に計算されました。地価は政府が調査して決定しました。米で納める年貢から、現金で納税する地租に変更されました。これにより、政府は税収を安定的に管理しやすくなりました。
背景と目的
税収の安定
明治政府は、富国強兵や殖産興業を進めるために、安定した財源を確保する必要がありました。
農村経済の変化
米ではなく現金で納税することで、国全体でお金を流通させ、経済を近代化させる狙いがありました。
結果と影響
地価の3%という税率は農民にとって重い負担となり、農村部では反発が起こりました。農作物が不作でも現金で納める必要があったため、生活が苦しくなる農民もいました。反発を受け、1877年には税率が3%から2.5%に引き下げられました。
地価の3%から2.5%に引き下げられた。
不満の高まり
地租改正が実施されると、多くの農民がその負担の重さに不満を抱き、各地で「地租改正反対一揆」が起こりました。特に収穫が少ない年には、納税が困難になり、一揆が激化しました。農民の反発を受け、1877年に地租の税率が地価の3%から2.5%に引き下げられました。この変更によって多少負担が軽減されましたが、農村経済にとっては依然として大きな負担でした。
ノルマントン号事件をきっかけに、国民が領事裁判権を撤廃する内容を求めた。
ノルマントン号事件とは
1886年(明治19年)、イギリスの商船ノルマントン号が和歌山県沖で沈没しました。船には日本人乗客25名が乗っていましたが、全員が救助されないまま犠牲になり、イギリス人船長と乗員だけが救助されました。
問題点
船長の対応が不適切で、日本人乗客を見捨てたと批判されました。しかし、船長はイギリス領事裁判所で軽い処分しか受けず、当時の不平等条約に基づく領事裁判権の不公平さが浮き彫りになりました。
直接国税を15円以上おさめた満25歳以上の男子。
有権者の条件
年齢満25歳以上の男子であること。
納税額直接国税を15円以上納めていること。
性別男性のみが対象で、女性には選挙権がありませんでした。
背景と影響
この条件を満たす人は日本の総人口(約4,300万人)の約1.1%、約45万人でした。主に地主や資産を持つ裕福な男性が有権者となり、農民や労働者などの一般層はほとんど選挙に参加できませんでした。政府は、当初から広範囲の人々に選挙権を与えることで混乱が起きることを恐れ、納税額などの厳しい条件を設けました。時代が進むにつれて選挙権の条件が緩和され、1925年には普通選挙法が制定され、25歳以上のすべての男子に選挙権が与えられるようになりました。
直接国税とは
納税者が自分の収入や財産に基づいて直接政府に納める税金のことです。
①地租(ちそ):土地にかかる税金。地価を基準に課税。
②営業税:商業や事業を行う人に課された税金。
③所得税:収入に応じて課される税金。
これに対して、商品の購入時に払う間接税(酒税など)は、直接国税には含まれません。
15円は現代の金額でいくらか
15円は、明治時代では非常に高額でした。当時の物価や給与をもとに現在の価値に換算すると、約30万円~50万円程度に相当すると考えられます。
日本の有権者の条件が変わっていく流れ
| 年号 | 法や制度の名称 | 有権者の条件 |
|---|---|---|
| 1890年 | 第1回衆議院議員総選挙 (旧選挙法) | – 満25歳以上の男子 – 直接国税15円以上を納める者 – 有権者は人口の約1.1% |
| 1925年 | 普通選挙法 | – 納税額の制限が撤廃 – 満25歳以上のすべての男子に選挙権 – 有権者は人口の約20% |
| 1945年 | 新選挙法 (男女普通選挙の実現) | – 満20歳以上の男女に選挙権 – 女性にも初めて選挙権が認められる |
| 2016年 | 選挙年齢引き下げ | – 満18歳以上の男女に選挙権 |
輸出量が輸入量を上回った。
変化の流れ
①輸入が中心だった時代
明治初期、日本では綿糸の多くをイギリスから輸入していました。イギリスは産業革命を経て綿工業が発達しており、安価で高品質な綿糸を大量に生産していたからです。
②国内生産の発展
日本でも明治時代に入ると、産業革命が進み、蒸気機関を活用した大規模な紡績工場が登場しました。特に、1877年に大阪紡績会社が設立され、その後国内で紡績業が急速に発展しました。
③輸出が輸入を上回る
1890年代には、日本の国内で生産される綿糸の量が増え、自国の需要を賄えるようになりました。また、余剰分をアジアの国々(特に中国や朝鮮)に輸出するようになり、1897年には日本の綿糸の輸出量が輸入量を上回る転換点を迎えました。
変化の背景
①技術革新
日本の紡績工場で新しい技術(蒸気機関やミュール紡績機)が取り入れられ、生産効率が大幅に向上しました。
②原料の確保
綿花を輸入して国内で加工する体制が整い、輸出用の綿糸の生産が可能になりました。
③アジア市場への進出
中国や朝鮮など近隣諸国への輸出が拡大し、日本製の綿糸が安定した需要を得るようになりました。
日本が綿糸を重視した理由
国内外での需要の高さ、生産体制の確立、そして工業化の第一歩としての適性にありました。綿糸は人々の生活必需品であり、国内市場だけでなく中国や朝鮮といったアジアの広大な市場でも安定した需要がありました。この需要を背景に、蒸気機関やミュール紡績機といった技術革新を取り入れることで、日本国内での大量生産が可能になり、輸入に頼らず自給自足を達成するだけでなく、輸出産業としても発展しました。
イギリスの産業革命の成功例を参考にした
日本が工業化を進める上で最初に取り組むべき分野として適していました。この成功を通じて得られた収益や技術、労働力の育成は、その後の鉄鋼業や重工業といった次の工業分野の発展の基盤となり、日本の近代化に大きな役割を果たしました。
日本が輸入依存から自立
さらに輸出主導型の産業へと成長する転換点をもたらしました。この流れは、単なる経済活動にとどまらず、明治政府が進める富国強兵政策や殖産興業政策とも密接に結びつき、近代国家への道筋を切り開く重要なステップとなったのです。
ロシアに対抗するため、軍備の拡張に使用された。
日清戦争に勝利した日本は下関条約を結び、清から賠償金や領土(遼東半島など)を獲得しましたが、三国干渉によって遼東半島を清に返還させられ、この屈辱がのちに日露戦争でロシアと対峙するきっかけとなりました。
賠償金の使い道と背景
①海軍力の増強
ロシアの極東進出に対抗するため、日本は強力な海軍を整備しました。賠償金を使い、イギリスから最新鋭の戦艦「三笠」などを購入し、艦隊の強化を図りました。
②陸軍の充実
北方からのロシアの脅威に備え、陸軍の装備を近代化しました。兵員の訓練や軍事施設の整備も進められ、日露戦争(1904年~1905年)での戦力強化につながりました。
③要塞の建設
ロシアとの対立が予想される地域に要塞を建設し、防衛力を高めました。特に朝鮮半島や日本海側での防衛体制が整備されました。
下関条約(1895年)の内容
領土の割譲
清は、日本に台湾、澎湖諸島(ほうこしょとう)、遼東半島を譲り渡しました。
賠償金の支払い
清は、日本に約2億両(テール)の賠償金を支払うことになりました。
朝鮮の独立承認
清は、朝鮮が独立した国家であることを認め、日本の影響力が朝鮮半島で強まりました。
下関条約がその名前で呼ばれる理由は、条約交渉と調印が山口県下関市にある春帆楼(しゅんぱんろう)という旅館で行われたためです。この地名が条約の名前として使われました。
清に勝ったのはすごいこと?
日清戦争(1894年~1895年)で日本が勝利したことは、当時の日本にとって非常に画期的で重要な出来事でした。東アジア最大の大国であった清を相手に勝利することは容易ではありませんでしたが、明治維新後の近代化によって日本は軍事力や経済力を大きく向上させ、戦争を有利に進めることができました。清は内部の腐敗や軍事の近代化の遅れにより弱体化しており、日本は最新の装備や訓練を整えた近代軍でこれを圧倒しました。この勝利により、日本は下関条約で領土(台湾など)や賠償金を獲得し、経済と軍事力をさらに強化しました。また、国際社会から「近代化を遂げた新興勢力」として認められ、列強の一員となる道を切り開きました。わずか30年ほど前まで鎖国していた日本が、短期間で近代化を成し遂げ、大国・清を打ち破ったことは、国際的に見ても非常にすごいことだったのです。
清に遼東半島を返還した。
下関条約(1895年)で獲得した遼東半島をめぐり、ロシア・ドイツ・フランスの三国干渉により、日本は清に返還を余儀なくされました。三国は「遼東半島の日本保有は清の安定を脅かす」として圧力をかけ、日本は国力が十分でないと判断し、要求を受け入れました。その代わり、日本は清から約3,000万両(テール)の追加賠償金を受け取りましたが、この屈辱により国内では対ロシア感情が悪化し、「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」のスローガンのもと国力強化が進められました。この経験は、後の日露戦争(1904年)でのロシアとの対決へとつながる重要な伏線となりました。
大型機械の導入と工場労働者の長時間労働によって生産が拡大した。
大型機械の導入
明治時代、日本では蒸気機関やミュール紡績機といった大型機械が導入され、大規模な紡績工場で効率的な大量生産が可能になりました。技術革新により、一度に多くの綿糸を生産できるようになり、生産量が飛躍的に増加しました。このような機械化の進展が、国内の紡績業を発展させた大きな要因となりました。
工場労働者の長時間労働
当時の工場労働者は、主に農村から集められた若い女性(女工)が中心で、彼女たちは長時間にわたる労働を強いられていました。一日の労働時間は12~14時間に及ぶこともあり、過酷な労働環境のもとで生産効率が高められました。労働者の努力と犠牲により、綿糸の生産量はさらに拡大しました。
ポーツマス条約で日清戦争のときより死者や戦費が多かったにも関わらず、ロシアから賠償金を得ることができなかったため。
日露戦争後に結ばれたポーツマス条約では、戦費や犠牲が大きかったにもかかわらず賠償金が得られなかったことから国民の不満が高まり、これが日比谷焼き討ち事件という暴動に発展しましたが、アメリカ大統領のルーズベルトが仲介役を務め、日本側の全権代表である小村寿太郎が冷静な交渉を行い、一定の成果を得た条約でもありました。
ポーツマス条約の主な内容(1905年)
ロシアは、日本に南樺太(サハリンの南半分)、満洲南部の鉄道や炭鉱などの経営権を譲渡しました。これにより、日本は満洲での影響力を強化しました。ロシアは、日本が朝鮮半島での指導的地位を持つことを承認しました。これにより、日本は後に朝鮮を保護国化する道を進むことになりました。日本が求めた戦争の賠償金については、ロシアが財政的事情を理由に拒否し、認められませんでした。
日比谷焼き討ち事件(1905年)
日露戦争で多くの犠牲を払いながらもポーツマス条約で賠償金を得られなかったことに国民が強く不満を抱き、東京の日比谷公園での抗議集会が暴動へと発展して警察署や新聞社が襲撃され、最終的に戒厳令が発布される大混乱となった明治時代を象徴する社会騒乱であり、この事件をきっかけに政府は国民との溝の深さを痛感し、近代日本の社会運動が次第に活発化するきっかけともなりました。
日清戦争と日露戦争の違い
| 項目 | 日清戦争 | 日露戦争 |
|---|---|---|
| 年号 | 1894年~1895年 | 1904年~1905年 |
| 死者 | 約1万3,000人 | 約8万8,000人(病死含む) |
| 戦費 | 約2億円 | 約17億円 |
| 賠償金 | 清から約3億1,000万円(2億両) | なし(賠償金は得られず) |
大正
第一次世界体制の大戦景気によって、日本の貿易は輸出額が輸入額を上回った。
変化の概要
第一次世界大戦の影響でヨーロッパの列強諸国が戦争に集中したため、アジアや他の地域への商品の供給が減少しました。その結果、日本はヨーロッパ諸国に代わり、アジアやアメリカ市場での製品供給を担うようになり、輸出が急増しました。綿製品や繊維製品、軍需品、雑貨など、日本の工業製品が多く輸出されるようになりました。特に、中国や東南アジアへの輸出が拡大しました。日本の貿易は第一次世界大戦を契機に輸出超過となり、大戦景気により経済が大きく成長しました。この時期、日本は貿易収支で黒字を記録し、外貨を獲得しました。
なぜ第一次世界大戦で好景気?
第一次世界大戦でヨーロッパの国々が戦争に集中して物を作れなくなったため、日本がその代わりに衣服の布や綿糸、鉄や船などを作ってアジアや世界にたくさん売り、工場が発展してお金を稼げるようになり、大戦景気と呼ばれる好景気になりました。
輸出額が輸入額を上回るとなぜ好景気になるのか?
他の国に商品をたくさん売ると、外国からたくさんのお金が入ってきます。お金が増えると、企業や工場はもっと生産を増やし、人々に給料を払えるので、経済が活発になります。輸出が増えると、工場や企業はたくさんの商品を作るために働く人を増やします。働く人が増えると、みんなが生活費やお買い物に使えるお金が増え、さらに経済が元気になります。
好景気の共通点
| 項目 | 共通点 | 例 |
|---|---|---|
| 背景 | 外部要因による景気拡大 | – 大戦景気:第一次世界大戦中のヨーロッパ諸国の供給不足 – 特需景気:朝鮮戦争でのアメリカ軍物資需要 – バブル景気:円高対応や金融緩和による資産バブル |
| 期間 | 短期間に急激な成長を記録 | – 大戦景気:1914年~1918年 – 特需景気:1950年~1953年 – バブル景気:1986年~1991年 |
| 分野 | 特定の産業や分野が好景気を牽引 | – 大戦景気:繊維、軍需 – 特需景気:鉄鋼、建設、化学 – バブル景気:不動産、金融、株式 |
| 影響 | 雇用の増加、所得の向上、一時的な生活水準の向上 | – 一時的に国民生活が豊かになるが、急激な変化によりバランスを欠く |
| 反動 | 好景気の後に必ず反動として不況や調整期が訪れる | – 大戦景気:戦後恐慌 – 特需景気:需要減少後の調整期 – バブル景気:バブル崩壊と不況 |
賃金よりも物価のほうが上昇したため。
第一次世界大戦中、労働者の生活が苦しくなった理由
需要の増加や輸入品の不足による物価の急上昇に対して、賃金(給料)の上昇が追いつかなかったためです。戦争の影響で軍需品や日用品の需要が増え、輸入品の供給が減ったことで、米をはじめとする食料品や生活必需品の価格が大幅に上昇しました。一方で、工場の生産量が増えて雇用が拡大したものの、賃金の上昇は物価ほど速くなく、働いていても生活費が家計を圧迫する状況に陥りました。
多くの男性が戦場にかりだされたため、工場では主に女性が働いていた。
男性の不足と女性労働者の増加
①男性が戦場へ動員
戦争が始まると、多くの男性が兵士として戦場に動員され、労働力が大幅に不足しました。工場や農場での仕事を担う男性がいなくなり、代わりに女性が働く必要が生じました。
②女性労働者の役割
工場では、武器や弾薬、軍服などの軍需品を生産する作業が中心でした。特に弾薬工場では、多くの女性が長時間働き、危険な化学物質を扱う過酷な作業を行っていました。
社会の認識の変化
女性が家庭の外で働く姿が当たり前となり、これまでの「女性は家庭を守るもの」という伝統的な価値観が揺らぎ始めました。戦争後、女性が「戦争中の働きに見合った権利を求める声」を上げるきっかけとなり、選挙権や労働環境改善の要求が広がりました。
女性の選挙権の拡大
第一次世界大戦後、女性に選挙権を与える国が増えました。
イギリス(1918年):30歳以上の女性に選挙権。
ドイツ(1919年):すべての成人女性に選挙権。
アメリカ(1920年):19条改正で女性参政権が認められる。
女性が社会や政治に参加する権利が拡大し、地位向上の基盤が築かれました。
シベリア出兵をみこして商人が米を買い占めたため。
ロシア革命による社会主義政権の誕生と国内の混乱を受けて、列強とともに日本はシベリア出兵を行い、多くの日本軍を派遣しましたが、これに伴う軍事費の負担や商人の米買い占めが原因で米騒動が発生し、当時の寺内正毅(てらうちまさたけ)内閣が総辞職しました。さらに出兵への批判が高まる中、国民の間では政治や社会改革を求める大正デモクラシーの動きが活発化しました。
シベリア出兵
1917年のロシア革命で社会主義政権が成立して国内が混乱したことを背景に、列強がロシア内戦に介入して反革命派(白軍)を支援する中、日本は社会主義の拡大阻止やシベリア鉄道・天然資源の確保といった経済的利益を目的として実施した軍事行動です。
日本軍の撤兵
他国(アメリカ・イギリス・フランスは1920年に撤兵)と比べて明らかに遅れましたが、その背景にはシベリアの経済的利益への期待や、社会主義拡大への強い警戒心、そして満洲・北方地域での影響力強化といった日本独自の戦略がありました。日本は1922年に撤兵を完了しましたが、経済的な成果はほとんど得られず、多額の軍事費だけが残りました。長期駐留が国際的な批判を招き、日本の孤立化を深める要因となりました。
米騒動(1918年)
米の価格が急激に上昇したことに対し、全国の農民や労働者、主婦たちが抗議運動や暴動を起こした日本初の大規模な社会運動です。この出来事は、米の買い占めや輸送制限による生活困窮が引き金となり、大正時代の日本社会に大きな衝撃を与えました。1918年7月、富山県の漁村で主婦たちが米価の高騰に抗議し、米問屋に対して安く米を売るよう要求したのがはじまり。全国で数百件以上の騒動が発生し、対応は後手に回りました。
寺内正毅内閣(てらうちまさたけ)
在任期間:1916年10月~1918年9月
シベリア出兵を決定した内閣。軍人出身で、強硬な軍事政策を推進。米騒動への対応が後手に回り、全国的な暴動を招いたことが大きな批判を浴びる。米騒動の責任を取って総辞職し、内閣が倒れる。
三大臣以外の大臣をすべて、衆議院の第一党である立憲政友会の党員がしめる本格的な政党内閣。
原敬内閣(はらたかし)(平民宰相)
在任期間:1918年9月~1921年11月
日本初の本格的な政党内閣(立憲政友会を基盤とした内閣)。大正デモクラシーを象徴する改革的な内閣で、庶民の支持を得た。シベリア出兵が長期化する中で撤兵を進めるが、財政負担が重く批判を受ける。内閣在任中に起きた鉄道拡張や学校建設などの公共事業は評価されたが、1921年に原敬暗殺事件が発生し、内閣が終わる。
政党内閣の基本的な仕組み
①国会と政党の関係
国会には、いろいろな政党が集まっています。その中で、一番多くの議席を持つ政党が「第一党」です。政党内閣では、この第一党が中心となり、首相(総理大臣)や大臣を選んで内閣を作ります。
②政党内閣の特徴
国会の第一党が政策を決めやすくなるので、国会での議論や法案の通過がスムーズに進むのが特徴です。一方、第一党が負ければ内閣が交代することもあります。
原敬内閣はどうして特別?
原敬内閣(1918年~1921年)は、日本で最初の本格的な政党内閣です。それまでの内閣では、大臣は軍人や官僚出身者が中心でした。原敬内閣では、「三大臣(外務、陸軍、海軍)」以外の大臣をすべて立憲政友会(原敬が属する政党)のメンバーが占めました。これにより、国会での議論がまとまりやすくなり、政策が進めやすくなったのです。
イメージしやすくする例
学校のクラスで生徒会を作るとき、「Aグループがいちばん多くのメンバーを集めた」とします。その場合、Aグループの代表が会長になり、他の役員もAグループのメンバーが担当する、という仕組みが政党内閣と似ています。つまり、第一党が中心となって、クラス全体(国会)をまとめる役割を果たすのです。
立憲政友会
設立年1900年(明治33年)設立者伊藤博文(初代内閣総理大臣)。国会での安定した政権運営を目指し、伊藤博文が立憲改進党や自由党などを統合して結成した。名前の「政友」は「政治の友」という意味で、国会を通じた政策決定を目指しました。立憲主義(憲法に基づく政治)を掲げ、国民の意見を政治に反映しようとした。1940年、立憲政友会は他の主要政党とともに大政翼賛会(たいせいよくさんかい)に吸収され、解党しました。
なぜ三大臣は政党が違う?
原敬内閣では、陸軍・海軍大臣は軍部の独立性を守るために現役の軍人から選ばれ、外務大臣は外交の専門性を重視して選ばれたため、立憲政友会以外の人物が務めました。それ以外の大臣は、立憲政友会が占める形で構成され、全体で14人の大臣による内閣でした。この仕組みが、原敬内閣を「本格的な政党内閣」と呼ぶ理由となっています。
納税額による制限がなくなり、満25歳以上の男子にかわった。
1925年の普通選挙法によって、納税額による制限がなくなり、満25歳以上のすべての男子に選挙権が与えられるようになりました。この改革により、有権者の数が大幅に増え、政治に対する国民の関心が高まるきっかけとなりました。しかし、女性に選挙権が認められるのは戦後の1945年まで待つ必要がありました。
納税額による制限の撤廃
それまでの選挙では、有権者になるために直接国税を15円以上納めていることが条件でした。このため、有権者は全人口のわずか1割以下で、主に地主や裕福な商人が対象でした。1925年の普通選挙法により、納税額による制限が撤廃され、より多くの人が選挙に参加できるようになりました。
有権者の条件
新しい条件は、満25歳以上の男子であることだけでした。経済的な条件がなくなったため、農民や労働者などの一般庶民にも選挙権が広がりました。
有権者数の増加
制限が撤廃されたことで、有権者の数は約300万人から1,250万人に大幅に増加しました。選挙に参加できる人が増えたことで、政治がより多くの国民の声を反映する可能性が高まりました。
昭和
共産主義の取締を強めるため。
背景
第一次世界大戦後の不安定な社会状況で世界的に社会主義や共産主義の思想が広がり、日本でも労働運動や農民運動が活発化していました。1917年のロシア革命によって社会主義国家(ソビエト連邦)が誕生したことが、日本の支配層にとって脅威と見なされました。国内の運動の活発化により、労働者の賃金改善を求めるストライキや農民の小作争議など、社会的な不満が高まりました。共産主義思想を広める日本共産党(1922年設立)も結成され、政府はこれらの動きを危険視しました。
治安維持法の制定から撤廃まで
制定(1925年)社会主義や共産主義を抑え、天皇制を守る目的で成立。
厳罰化(1928年)死刑を含む罰則追加、思想弾圧が強化。
戦時期の利用(1930年代~1945年)戦争体制の維持や言論統制に活用。
撤廃(1945年)戦後、GHQの指示により廃止され、思想・言論の自由が確保。
治安維持法は、戦前・戦中の日本における思想弾圧の象徴的な法律であり、その影響は日本の政治や社会に深い傷跡を残しました。
法の目的
天皇制と国体(国家の体制)の維持が目的。社会主義や共産主義は「天皇制の廃止」や「私有財産の否定」を掲げており、政府はこれを国家の基盤を脅かすものと考えました。治安維持法は、天皇制を守り、国家の安定を維持することを目的として制定されました。社会主義、共産主義のような過激な思想を広めたり、これに基づいて運動を行うことを禁止しました。
共産主義の基本的な考え方
①私有財産の否定
個人が土地や工場などを「自分のもの」として所有するのではなく、それらを社会全体で共有します。これにより、貧富の差をなくそうとします。
②平等な社会
富や資源をみんなで平等に分け合い、誰もが同じように暮らせる社会を目指します。貧富の格差や不平等を解消することが目標です。
③労働と報酬
働ける人はみんなで協力して生産活動を行い、その成果を公平に分け合います。「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」という考え方が基本です。
社会主義と共産主義
共産主義は、すべてを共有する完全な平等を目指す理想的な社会ですが、現実には実現が難しいとされます。社会主義は、格差を減らしつつ資本主義を活かす現実的な仕組みであり、北欧諸国などで成功例があります。大きな違いは、共産主義が財産のすべてを共有することを目指すのに対し、社会主義は一部の私有財産を認める点です。
主義
| 項目 | 社会主義 | 共産主義 | 資本主義 |
|---|---|---|---|
| 国 | スウェーデン、デンマークなど | 旧ソ連、中国 | アメリカ、イギリス、日本、韓国 |
| 経済の仕組み | 市場経済と政府の調整を組み合わせる。 | 政府主導の計画経済(市場経済を否定)。 | 市場経済(自由競争)が基本で、政府の介入は少ない。 |
| メリット | 貧富の差が小さく、教育や医療が充実。 | 格差がなく、すべての人が平等な生活を送れる理想。 | 自由な競争が経済を発展させ、効率が良い。 |
| デメリット | 税金が高く、政府の介入が多い。 | 政府の統制が強く、個人の自由が制限される。 | 格差が広がり、貧困層が生じやすい。 |
金融危機によって、銀行が倒産する前に預金を引き出すため。
1927年に銀行に人々が押しかけた理由
金融危機で銀行が倒産するという噂が広がり、自分の預金を守るために引き出しを急いだからです。この金融恐慌は関東大震災(1923年)の影響や震災手形問題が背景にあり、銀行倒産や経済の混乱を招きました。この出来事をきっかけに、銀行の管理や金融制度の見直しが進められるようになりました。
恐慌の連続
金融恐慌(1927年)銀行危機が経済不安を招き、日本経済が脆弱化。
世界恐慌(1929年)日本の輸出依存型経済が打撃を受け、農村が大きな影響を受ける。
昭和恐慌(1930~1931年)金解禁が失敗し、農村・都市の両方で経済苦が広がる。最終的に金本位制廃止で収束。
これらの出来事は、連続して起こり、日本経済の脆弱性と国際経済への依存の深さを浮き彫りにしました。
小作農の収入が少なくなると、小作争議の件数が増加した。
植民地との関係を密接にして、貿易を拡大すること。
国際連盟で満州国を認めず、日本軍の占領地からの撤兵を求める内容が決議され、日本は国際連盟を脱退した。
犬養毅内閣は満州国を認めませんでした。2017_4
中国の援蒋ルートを断ち切るために南進。アメリカは石油の輸出を禁止。
満20歳以上の男女に選挙権が与えられたため、有権者数は大きく増加した。
政府が地主から強制的に買い上げた小作地を、小作人に安く売り渡した。その結果、農地面積に占める自作地の割合が増加した。
アメリカを中心とする資本主義の西側陣営と、ソ連を中心とする共産主義の東側陣営の対立。
当初は戦争を起こさない国にする基本方針だったが、1948年に日本を西側陣営の一員にする方針に転換した。
朝鮮戦争がおこり、アメリカ軍向けの軍需物資を日本で生産したため特需景気になった。
主権を回復した。
日本経済は高度経済成長の時期だったため。
石油危機きよって、物価が上昇し景気が悪化した。
まとめ
解説部分を今後補強予定~
ひとまず問題と答えだけ~